(1)変動損益計算書とは
変動損益計算書は、医業収益から変動費を控除し限界利益を表示する様式で、直接原価計算様式ともいわれます。通常の損益計算書に比べて利益予測や利益計画に役立つなど、戦略的に優れています。
【財務会計における損益計算書の計算式】
医業収益 − 医業費用 = 医業利益
医業利益+ 医業外収益 − 医業外費用 = 経常利益 |
【管理会計における変動損益計算書の計算式】
医業収益 − 変動費 = 限界利益
限界利益 − 固定費 =経常利益 |
限界利益は、医業収益が1単位増えるごとの増加利益を表しています。
医業収益に対する限界利益の割合を限界利益率といいます。
| 限界利益率 |
= 限界利益÷医業収益×100 |
| |
=(医業収益−変動費)÷医業収益×100 |
| |
= 1−変動費率 |
|
【例】
(2)費用の性質
医業費用の中には、医業収益の増減に応じて変化する変動費もあれば、医業収益の増減に関係なく毎期発生する固定費もあります。
よって、費用を変動費と固定費に分けて捉えることによって、病医院の収益性をより正確に把握することができます。
また、変動費と固定費では費用の性質が異なるので、削減方法も自ずと異なります。よって、コストダウンを図る場合にも、変動費と固定費に分けて検討することが大切です。
| ① |
変動費 |
| |
変動費とは、医業収益の変化に伴って比例的に発生する費用で、医薬品費、診療材料費、検査委託費、残業手当、歩合給などがあります。 |
| |
|
| ② |
固定費 |
| |
固定費とは、医業収益の変化に関わりなく発生する固定的な費用であり、仮に診療報酬がゼロであっても発生する費用です。固定費には人件費、減価償却費、賃借料のほか通常の支払経費などがあります。 |
| |
|
| ③ |
準変動費・準固定費 |
| |
全ての費用項目が、純然たる変動費、固定費に区分できるわけではありません。
電力料、ガス代、水道料のように、基本料金の存在等によって診療がゼロであっても発生するものの、業務時間の変化に応じて比例的に発生するものを準変動費と考え、より実態に合った費用区分をすべきです。 |
(3)変動費・固定費の分解方法(固変分解)
| ① |
個別費用法 |
| |
個々の費用科目ごとに変動費、固定費の分解をするのが個別費用法であり、以下の2通りの方法があります。 |
| |
|
| |
| イ) |
科目を要素別に分解して固定部分は固定費・変動部分は変動費とする方法 |
| ロ) |
科目の性質によって変動費に近いものは変動費とみなし、残りを固定費とする方法 |
|
|
|
| |
|
| |
イ)の方がより厳密ですが、作成コストや分かりやすさを考慮すれば、ロ)の変動費を主要なものに絞り、残りを固定費とするやり方でも差し支えありません。 |
| |
|
| ② |
分解例 |
| |
| |
医業 |
| 変動費 |
医薬品費+診療材料費+検査委託費+外注費等 |
| 固定費 |
その他の費用 |
|
| |
その他、病医院の実情に応じて重要な変動費がある場合は、適宜加えます。 |
(4)変動損益計算書を3期比較する
●A病院の事例
【損益計算書分析】
3期比較変動損益計算書分析
【分析ポイント1 大筋で傾向をとらえる】
決算書分析では、まず大枠で収益状況がどのようになっているかを捉えます。傾向は上記の4つのパターンに分類できます。
増収増益であれば、過去の取り組みが経営成果となって現われていることになりますし、減収減益であれば過去の取り組みが不十分であったか、取組方針が間違っていた、競合の発生、などが挙げられます。
【分析ポイント2 その傾向の要因分析をする】
| ① |
収益の傾向 |
| |
| ● |
医業収益の推移 |
| |
| イ)増加要因: |
患者数の増加、実日数の増加、レセプト単価の上昇、診療報酬点数の上昇 |
| ロ)減少要因: |
患者数の減少、実日数の減少、競合の発生 |
|
|
| |
|
| ② |
3つの利益推移 |
| |
| ● |
限界利益の推移 |
| |
| イ)増加要因: |
変動費率の低下、診療材料費の低下、委託費(外注費)の低下 |
| ロ)減少要因: |
変動費率の上昇、レセプト単価の低下、材料費の増加、委託費(外注費)の増加 |
|
| |
|
| ● |
医業利益の推移 |
| |
| イ)増加要因: |
人件費の減少、その他固定費の減少 |
| ロ)減少要因: |
人件費の増加、その他固定費(不動産賃借料、水道光熱費、通信費、減価償却費、旅費交通費、接待交際費等の増加) |
|
| |
|
| ● |
経常利益の推移 |
| |
| イ)増加要因: |
支払利息の減少、受取利息・配当金の増加、雑収入の増加 |
| ロ)減少要因: |
支払利息の増加、受取利息・配当金の減少、雑収入の減少 |
|
|
| |
|
| ③ |
部門別損益を分析する |
| |
●患者数、実日数の増減を分析する
●診療行為別の医業収益分析をする |
| |
|
| |
医業収益や利益の増減を分析するには、この診療行為別分析が必須です。 |
|
大枠での傾向がつかめたら、その傾向を生み出した要因を探っていきます。
分析の項目は①医業収益の推移、②三大利益(限界利益、医業利益、経常利益)の推移、③診療行為別の推移の3項目となります。
【分析ポイント1 事例病医院A医院の分析】
<医業収益> <経常利益>
平成16年1月期 1,217,167千円 16,688千円
平成17年1月期 1,156,443千円 △60,724千円 5,484千円 △11,204千円
平成18年1月期 1,212,560千円 +56,117千円 9,332千円 + 3,848千円
直近2年間だけをみると、「増収・増益」となっているが、2年前の医業収益と経常利益からみると医業収益は同水準になっているが、経常利益は大きく減少しており、「減収・減益」と判断できる。
|
【分析ポイント2 事例病医院A医院の分析】
| ① |
医業収益の傾向 |
| |
平成16年1月期 1,217,167千円
平成17年1月期 1,156,443千円 △60,724千円
平成18年1月期 1,212,560千円 +56,117千円 |
| |
医業収益は平成17年1月期に減少しているが、平成18年1月期には2年前の水準に戻している。 |
| |
|
| ② |
三大利益の推移 |
| |
●限界利益の推移 |
| |
平成16年1月期 365,311千円
平成17年1月期 361,131千円 △ 4,180千円
平成18年1月期 382,210千円 +21,0797千円 |
| |
|
| |
●医業利益の推移 |
| |
平成16年1月期 28,286千円
平成17年1月期 11,190千円 △17,096千円
平成18年1月期 37,800千円 +26,610千円 |
| |
|
| |
●経常利益の推移 |
| |
平成16年1月期 16,688千円
平成17年1月期 5,484千円 △11,204千円
平成18年1月期 9,332千円 + 3,848千円 |
| |
|
| |
平成17年1月期には3つの利益とも減少しているが、平成18年1月期には回復。
しかし、経常利益は平成16年1月期の水準には回復していない。 |
|
【三大利益を左右する経費の推移】
| ● |
変動費の推移 |
| |
平成16年1月期 851,856千円
平成17年1月期 795,312千円 △56,544千円
平成18年1月期 830,350千円 +35,038千円 |
| |
|
| ● |
人件費の推移 |
| |
平成16年1月期 241,419千円
平成17年1月期 257,134千円 +15,715千円
平成18年1月期 264,300千円 + 7,166千円 |
| |
| 【増加科目】 |
役員報酬、給与手当、法定福利費 |
| 【減少科目】 |
雑給、賞与、福利厚生費、その他人件費 |
|
| |
職員数の増加(+1名)、役員の増加(新任2名、退任1名)、これらに伴う法定福利費が増加している。 |
| |
|
| ● |
その他固定費の推移 |
| |
平成16年1月期 95,606千円
平成17年1月期 92,807千円 △ 2,799千円
平成18年1月期 80,110千円 △12,697千円 |
| |
| 【増加科目】 |
保険料 |
| 【減少科目】 |
交際費、減価償却費、消耗品費、車両費、修繕費、租税公課、広告宣伝費 |
|
| |
役員増加に伴う保険料(病医院防衛)の増加 |
| |
広告宣伝費(DM、野立看板)の減少→効果なしに伴う減少 |
| |
|
| ● |
医業利益の推移 |
| |
増加の大半は、役員の退任に伴う退職慰労金の発生によるもの。これに関しては一時的なものであるため大きな問題ではない。 |
| |
|
| ● |
特別損失の増加 |
|
【3つの分析ポイントから抽出した問題点】
| ① |
人件費の増加 |
| |
●賞与は減少しているが、給与自体は増加している。
●役員報酬の増加(2名増加) |
| |
|
| ② |
人件費以外の固定費では、保険料の増加が突出している |
| |
→役員保険への加入 |
| |
|
| ③ |
限界利益は増加しているが、棚卸資産も増加しているため利益の調整がないかを確認する必要がある |
| |
→棚卸資産の水増しが判明 |
| |
|
| ④ |
その他 |
| |
営業外費用、役員退任に伴う退職慰労金支払のためであり、一時的な増加のため問題点には挙げていない。
しかし、支払利息は増加傾向にあるため、金利の交渉などが必要となる。 |
|
変動費は医業収益に比例して増減しますが、医薬品費、診療材料費や検査委託費(外注費)など外的要因で価格が高騰し医業収益と関係なく増加するものもあります。調達先を吟味し、条件のよい先への切替えなどを検討しなければなりません。また、病医院内でも不良在庫の一掃、歩留まりの向上などマイナス要因を除去する取り組みを怠ると、変動費は自然と増加します。
仕入先や外注先との長い取引きの中で仕入代や外注費の削減は、慣れあいの関係なため、言い出しにくいことは非常に多くあります。
しかし、変動費の削減は非常に重要です。発想を変えて、明日から今と同じビジネスを始めるとしたら、どこから仕入れるか、どこに外注を頼むかなど、当然、安くて質のいい会社を探します。
その発想で再度、仕入先、外注先を再検討してみる必要があります。
固定費は増加した科目を精査し、増加の要因に妥当性があるか検討しなければなりません。固定費はすべて圧縮すべきものではないからです。
人件費は適正な労働分配率の範囲内にあるかを見ます。また、政策的に人材を採用した場合は生産性が向上したかを確認します。治験費など将来の利益確保に向けてかけるべき費用(利益貢献経費)についても妥当性を吟味します。唯一圧縮して良い固定費は節減可能費としてとらえ、可能な限り圧縮させることです。
「販管費は削減しない」という考え方もあります。医業収益が下がっているときに販管費を削減するとますます収益が下がります。
当たり前の事なのですが、不況になると広告宣伝費削減、といった話がすぐ出てきます。
同じく利益貢献費の削減も然りです。研究研修費や教育訓練費といった投資費用も不況時のコストダウン項目に上がりがちです。
固定費を削減するリストラ政策で利益のバランスをとろうとし続けると、固定費削減→付加価値減少→固定費削減→付加価値減少となっていって利益はゼロになってしまいます。
不況下においても経営とは常に何に投資すべきかを考えないといけないのです。
(1)生産性と付加価値
病医院が生み出す付加価値を数値的にとらえるとともに、その産出効率を測る指標について学びます。具体的には、人的資源を投入することによる労働生産性、資本投入することによる資本生産性等です。
生産性とは、本来、生産活動において投入に対する産出の効率を把握するために使われている概念です。これを財務分析に応用したものが、ここでの生産性分析です。財務分析における生産性では、産出には付加価値が使用され、投入には労働や資本が使われます。付加価値とは、その病医院が経営活動において"創造した価値"を意味し、具体的には、中小企業庁方式(控除法)と、日銀方式(加算法)の2つの計算法が代表的です。
| ① |
中小企業庁方式 |
| |
生産高(≒医業収益)から外部購入高である医薬品費、診療材料費、検査委託費、外注加工費、を控除して計算され、限界利益と呼ばれています。 |
| |
|
| ② |
日銀方式 |
| |
付加価値の構成要素である経常利益、人件費、金融費用、賃借料、租税公課、減価償却費を加算して計算されます。 |
| |
| ● |
中小企業庁方式 : |
| |
医業収益−(医薬品費+診療材料費+外注加工費+検査委託費) |
| ● |
日銀方式 : |
| |
経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課+減価償却費 |
|
|
| |
|
| |
生産性分析の中心は付加価値生産性の分析です。これは一定の資源投入に対してどの程度の付加価値を得ているかを示すもので、資源投入の観点から、労働生産性と資本生産性が中心となります。 |
(2)労働生産性分析で一人当たりの効率をみる
労働投入に対してどの程度の付加価値を上げているかを意味し、具体的には役職員1人当たりの付加価値額という指標で分析されます。この指標は付加価値額を職員数で割って計算しますが、職員数は正規従業員の所定労働時間に換算しなければなりません。
この指標を生産高で交差させると下記のような展開となり、これより労働生産性を高める方策として次の事項が誘導されます。
| ① |
付加価値率を高めること |
| ② |
作業改善等によって労働効率を高めて、職員1人当たりの収益を高める |
|
| ① |
人件費は総額人件費で把握する |
| |
人件費は、どの病医院にとっても三大経費の一つになっています。総額人件費が経営に与えている影響を分析し、人件費が病医院にとって適正な水準であるかを確認し、今後の総額人件費の目標を設定します。
特に重要な指標は「労働分配率」「1人当り医業収益」「1人当り付加価値(労働生産性)」「1人当り経常利益」「1人当り人件費」です。業界平均値と比較することにより、経営改善の切り口を発見することができます。 |
| |
|
| ② |
付加価値の分配と労働分配率 |
| |
医院が得た付加価値は、例えば人件費、設備投資、内部留保というようにさまざまな形に配分されることになります。この配分のバランスがくずれた場合、経営上の問題が引き起こされることになるため、適正に実施される必要があります。
付加価値に占める割合で最も大きい金額となるのは人件費です。人件費に係る代表的な指標として、その適正度合いを分析するのが労働分配率です。労働分配率は、人件費を付加価値で割って計算されます。これが大きくなると人件費負担が大きくなることを意味しています。
日本の病医院の労働分配率は、平均で62%強となっています。この比率は高ければ高いほど「ヒト」による仕事が多いことを示します。「ヒト」の力で仕事をする部分が他医院に比べて大きい場合、たいていは生産性があまりよくないという評価をすることになります。
したがって、労働分配率は同じ業界の中で他社と比較して高いか低いかが問題となってくるわけです。
この式の意味は、医業収益に占める人件費の割合を減らすか、医業収益に占める付加価値の割合を増やせば、労働分配率が小さくなることを表しています。
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
人件費/職員数は「1人当たりの人件費」で給与水準を表します。一方、付加価値/職員数は「労働生産性」です。
病医院としては給与水準をおさえて、なおかつ労働生産性を上げれば、労働分配率が下がり、病医院の生産性が向上することがわかります。 |
| |
|
| |
|
| |
この式より、平均賃金を下げるか、職員を減らすことにより労働分配率が小さくなることがわかります。平均賃金を下げる手段としては、正規職員のパート化などが考えられます。また、職員数を減らす手段としては、能力開発により職員の生産性を向上させることが考えられます。 |
【A病院の事例】
●生産性・成長性分析
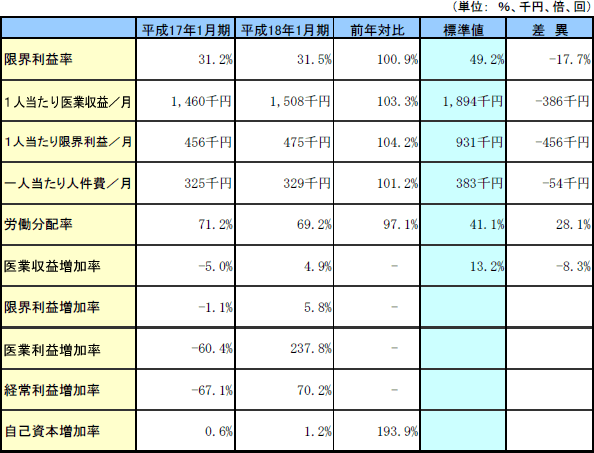 |
| ※標準値はTKC BAST 一般病院の黒字企業の黒字企業平均値 |
【生産性分析から抽出した問題点】
| ① |
限界利益率が低い |
・・・仕入の見直しが必要 |
| ② |
一人当たり医業収益が少ない |
 |
| ● |
一人当たり人件費は高くないため、職員数が多いと判断できる |
| ● |
一人当たり限界利益の増加 |
|
| ③ |
一人当たり限界利益が少ない |
| ④ |
労働分配率が高い |
|
(1)損益分岐点とは
損益分岐点とは、収益の額と費用の額が等しくなる点、すなわち利益も損失も生じていない医業収益、いわゆる採算点を言います。
損益分岐点医業収益は以下のように固定費を限界利益率で除しても求められます。
(2)損益分岐点図表(売上・費用・損益関係図)とは
損益分岐点を求める算式により、損益分岐点を図表化することができます。この図表により損益分岐点を可視化できるだけでなく、利益を増加させる方法をコスト面からイメージすることができます。
(3)損益分岐点比率で自病医院の経営安全度がわかる
現状または想定している医業収益が、損益分岐点医業収益と比較してどの位置にあるのかを示すのが損益分岐点比率で、100%から損益分岐点比率を差し引いたものが経営安全度です。
これらは、以下の算式で表されます。
損益分岐点比率=損益分岐点医業収益÷実際医業収益(%)
経営安全度=(医業収益−損益分岐点医業収益)÷実際医業収益(%) |
損益分岐点比率が高いか低いかにより、病医院の収益獲得能力面での安全度が判断できます。損益分岐点比率は低いほど、現状または想定している医業収益が損益分岐点医業収益を上回っていることを意味し、損益構造上望ましいと言えます。つまり、損益分岐点が低ければ低いほど、病医院はより少ない医業収益で利益を得ることができます。損益分岐点が低いということは、その病医院が医業収入の減少というリスクに強いことを意味します。
経営安全度については、高ければ現状または想定している医業収益が損益分岐点医業収益に対して余裕を持っていることになります。
(4)事例病医院の分析結果と問題点
【A病院の事例】
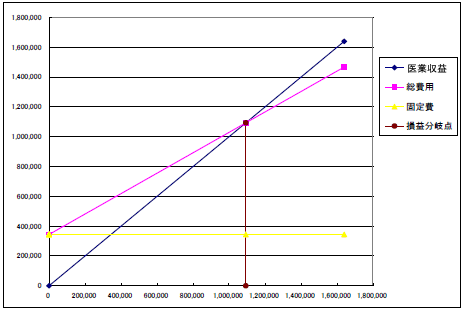
【損益分岐点分析から抽出した問題点】
| 損益分岐点比率が高い・・・ |
損益分岐点の引き下げ→固定費の削減と変動費(仕入)の削減 |
| |
目標としては85%程度 |
|
【損益分岐点比率を下げるポイント 】
損益分岐点を下げ、不況耐久力を付けるためには、病医院としては、いくつかの方策があります。
1つは、限界利益率を上げること、言い換えれば変動費(率)を下げることです。具体的には、仕入、診療材料費、外注費、検査委託費の削減等がこれにあたります。
もう1つは、固定費を削減することです。
具体的には、正職員を減らしパートタイム・アルバイト、などのより弾力的な雇用への切り替え、外注、アウトソーシング等がこれに相当します。
(1)結果指標
医業活動の結果は利益とキャッシュによって捉えられます。よってこれらは「結果指標」として管理します。
| 【損益項目の結果指標】 |
●経常利益の確保(医業収益経常利益率) |
| |
|
| 【キャッシュ項目の結果指標】 |
●営業キャッシュフローの確保 |
|
(2)要因指標
利益は、収益確保、変動費の削減(限界利益増加)、固定費の圧縮によって積上げられたものです。
よって医業収益、経費等は「要因指標」になります。要因指標を管理することで結果指標である利益の確保が可能になります。
【損益項目の要因指標】
● 医業収益の確保
● 変動費の減少
● 限界利益の確保
● 人件費の圧縮
● 人件費外固定費の圧縮 |
医業収益・利益は下限目標、すなわち必達目標であり下回ることは許されないことになります。
変動費、固定費などの経費目標は枠内に収める上限目標であり、必守目標になります。
(3)プロセス指標
売上、利益の目標を設定した段階で目標達成のための必要な活動量は決まってきます。この活動の量と質を管理することが重要になります。よって活動計画で管理すべき「プロセス指標」を業績管理に含める必要があります。
プロセス指標とは、要因指標の目標を達成するための活動を明確にしたものです。多くの病医院では、要因指標の把握までにとどまっており、「前月は利益が減った。来月は必ず増加させるように!」という管理になってしまっている傾向があります。これでは、毎月同じことの繰り返しで、外部環境が良い時は目標達成できますが、悪い時は達成できない成り行き経営になってしまいます。
逆に、結果指標である経常利益を確実に上げている病医院では、結果指標や、要因指標ではなく、プロセス指標の管理を重点的に行っており、常に小さな改善、創意工夫を行っています。
例えば新規患者拡大については、今年度新規患者による増収をどれだけ見込むのか、その増収部分を報酬単価で割ると何人の増患が必要なのかが分かります。
また、既存患者に対しては、従来どおりの来院を継続できたかという点がポイントです。既存患者を守るために患者の取り巻く環境を把握し、ニーズを的確に捉え、課題を解決する診療方法を提案をし患者シェアを高めることと、患者を失う原因となるクレームの減少を図ります。
【プロセス指標】
【既存患者維持】
●既存患者継続率
●既存患者数
●来院回数・レセプト単価 |
| |
【職員レベルアップ】
●スタッフ育成度
●研修回数
●アウトプット回数 |
|
| |