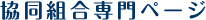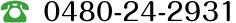協同組合の概要
協同組合の特徴
① 基準
- 1.相互扶助目的:組合は組合員の相互扶助を目的とするもの
- 2.加入脱退の自由:強制的に加入させられたり、脱退させられることはない
- 3.議決権・選挙権の平等:出資の多寡にかかわらず、一人一票
- 4.剰余金配当の基準:原則として、組合事業の利用に応じて分配する
② 原則
- 1.直接奉仕の原則:組合は組合員の事業に対して直接的な奉仕を行う
- 2.政治的中立の原則:組合は政治団体ではなく、経済団体である
株式会社との違い
| 株式会社 | 事業協同組合 | |
| 組織の目的 | あり | あり |
| 設立 | 自由 | 行政庁の認可 |
| 出資者資格 | 自由 | 地区内の中小事業者 |
| 出資限度 | 自由 | (1社又は1人)25%まで |
| 議決権 | 1株1票 | 1人1票 |
| 出資配当 | 自由 | 出資の10%が限度 |
| 利用分量配当 | なし | 事業利益の応分の還元 |
| 決算書 |
貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 個別注記表 付属明細表 |
財産目録 貸借対照表 損益計算書 剰余金処分案(損失処理案) |
定款
| 内容 | ひな型条文 | ポイント |
|---|---|---|
| 目的 | 第1条 | 協同組合のポイントである相互扶助を謳っています。 |
| 名称 | 第2条 | 「協同組合」を名称の前後につける必要があります。 |
| 地区 | 第3条 | 組合員の範囲を限定します。 |
| 事務所所在地 | 第4条 | 組合の事務所所在地(市町村)を記載します。組合の地区内である必要があります。 |
| 公告方法 | 第5条 | 組合の掲示板、官報、日刊新聞等を定めます。 |
| 規約等 | 第6条 | 規約や規程の設定・変更廃止についての方法を定めます。 |
| 事業 | 第7条 | 組合の実施する事業を記載します。明確な表現で具体的に列挙する必要があります。 |
| 組合員資格 | 第8条 | 組合員になるための資格を記載します。どのような事業者を組合員にするのか表現の工夫が必要です。 |
| 加入 | 第9条 | 組合員資格のある者は、原則誰でも組合に加入できます。 |
| 加入者の出資払込 | 第10条 | 加入予定者は遅滞なく出資金を組合へ支払わなければいけません。 |
| 脱退者の持分払戻 | 第14条 | 持分の払戻基準は必ず定款に定めなければいけません。 |
組合員の加入
①加入の自由
組合員の資格を有する者(組合の定款に記載されている地区内の資格を有する事業者)は、原則加入は自由です。組合は加入を拒んだり、現在の組合員より困難な条件を付すことはできません。
②例外的取扱い(加入拒否の正当な理由)
下記理由等があれば加入を拒否できる場合もあります。
- 加入申込者の規模が大きく、組合の民主的運営が阻害される又は独占禁止法が適用される恐れがある場合
- 除名直後の加入申し込みをした場合、除名理由の原因が解消していない場合、加入申し込み前に組合の活動を妨害していた場合
- その者の加入により内部秩序が乱される又は著しい信用低下を招く場合
- 組合員の情報・技術等の経営資源の機密保持ができなくなる場合
- 組合事業のキャパシティーから組合員の増加により円滑な運営が不可能になる場合
③加入の種類
加入の種類 |
原始加入 | |
持分承継加入 |
相続加入 | |
| 譲受加入 | ||
脱退時の処理
① 脱退の方法
- 自由脱退:組合員の意思で脱退することができ、事業年度終わりに脱退となります
- 法定脱退:組合員の意思にかかわらず、法定事由が生じた時に脱退となります
② 自由脱退
組合員は90日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて脱退することができます。90日の予告期間は定款で1年まで延長することが
できます。
③ 法定脱退
主に次の事由によって、法定脱退となります。
- 組合員の資格の喪失
- 死亡(個人事業主)又は解散(法人事業主)
- 除名
④ 除名
下記事由の組合員が対象となります。(なお、除名するには総会の特別議決が必要です)
- 長期にわたり組合事業を利用しない場合
- 組合に対する義務を怠った場合
- その他定款に定める事由に該当した場合
⑤ 持分の払戻
| 基準額 | 組合財産の時価評価額 |
|---|---|
| 算定時期 | 払戻事由の発生した事業年度末 |
| 払戻額 | 定款の定めによる(一般的には3種類)
1.出資額限度 2.簿価限度額 3.全額払い戻し |
| 払戻時期 | 一般的には通常総会後 |
| その他 | 払戻請求権の時効は2年、法解釈では組合債権との相殺も可能 |