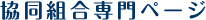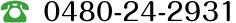協同組合の会計
組合法上の決算書
① 組合特有の決算書類
-
財産目録
財産目録は、組合が所有している資産、義務を負っている負債の内容を表示する書類です。財産目録に付すべき価額は、原則として取得原価基準となっています。時価情報については、財産目録の脚注に時価による組合正味財産の価額を表示します。 -
貸借対照表・損益計算書
基本的には株式会社で使用する決算書と同様ですが、一部勘定科目や区分が異なるため注意が必要です。【参考】 >> 協同組合の貸借対照表と損益計算書
-
剰余金処分案又は損失処理案
株式会社では会社法移行時に株主資本等変動計算書に変更されましたが、組合決算書においては「剰余金処分案又は損失処理案」は作成が義務付けられています。一方で、会社法で求められている株主資本等変動計算書は作成する必要はありません。
剰余金処分について
① 利益準備金
当期純利益(繰越損失がある場合にはこれを控除した金額)の10分の1以上を利益準備金として積み立てなければいけません。会社法上は配当時のみ積み立てを強制されるため、注意が必要です。
利益準備金は、定款で定める額に達するまで(一般的には出資総額の2分の1)は積み立てなければならず、損失の填補以外は取り崩すことができません。
② 教育情報費用繰越金
当期純利益(繰越損失がある場合にはこれを控除した金額)の20分の1以上を教育情報費用繰越金として繰り越さなければいけません。
教育情報費用繰越金は、組合員の事業に関する経営及び技術の向上または組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業のために積み立てる繰越金であり、教育情報事業の実施に際し取崩し、収益に計上されることになります。
③ 積立金
定款で定める積立金として、特別積立金と言われるものがあります。特別積立金は、定款規定により当期純利益(繰越損失がある場合にはこれを控除した金額)の10分の1以上を積み立てる必要があります。特別積立金は原則として損失填補にのみ使用できますが、定款の規定により出資総額を超える部分については、総会議決により損失填補以外の目的にも使用することができます。
その他の任意積立金、例えば施設修繕積立金や周年記念事業積立金等は総会の議決により積立て、その積立目的に従い取り崩すことができます。
④ 配当金
-
出資配当
組合は配当可能限度額の範囲内であれば無制限に配当できる株式会社とは違い、出資額の10%を超えて配当することはできません。
それは、組合の目的は組合員の相互扶助であり、営利追求ではないことや、直接奉仕の原則から、組合員への奉仕は組合で獲得した利益を分配するという間接的な奉仕は、本来の組合の姿とは言えないからです。 -
事業利用分量配当
事業利用分量配当とは、組合の利益の源泉を組合員から徴収した手数料等が多額であったことと考え、利益を組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する(返還する)ものです。
事業利用分量配当金には、出資配当のような制限はなく、一定の範囲内であれば自由に行うことができます。
なお、事業利用分量配当は組合税務において非常に重要な役割を有しています。この処理を誤ると組合に対しても組合員に対しても不利な影響を及ぼすことがありますので、事業利用分量配当を行う場合には注意が必要です。