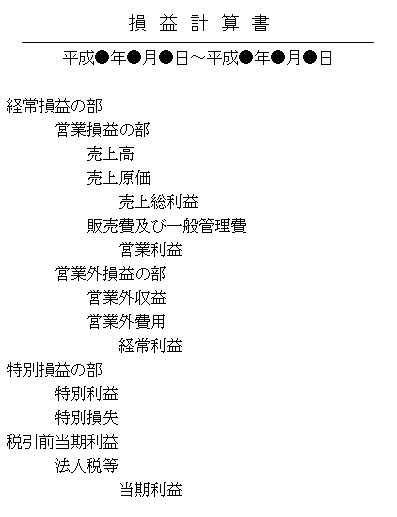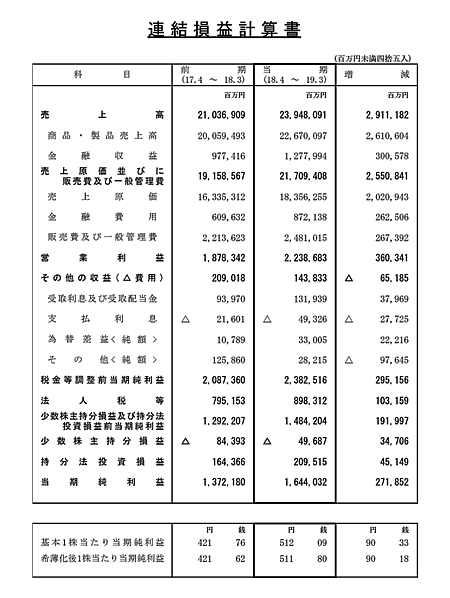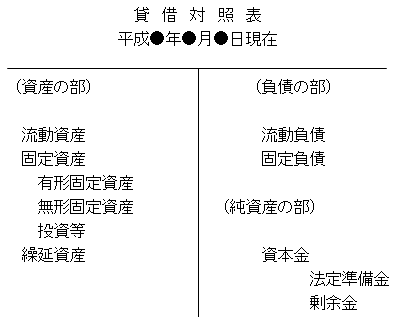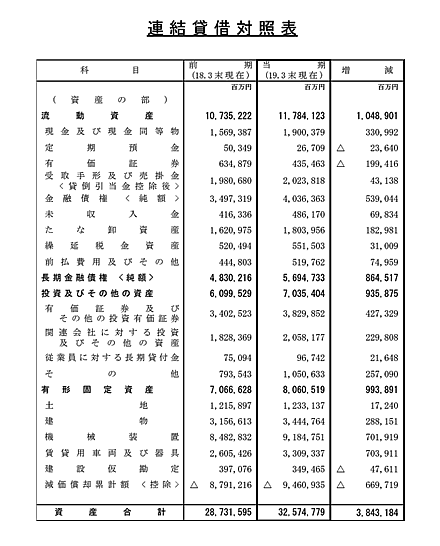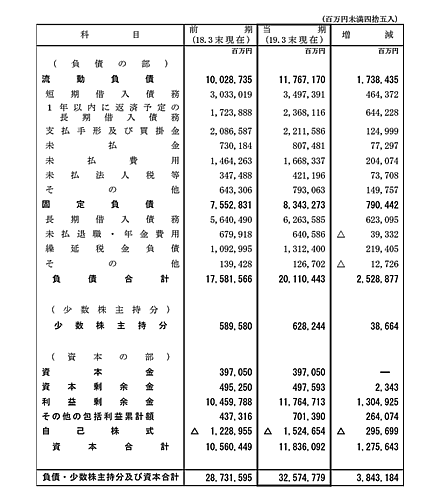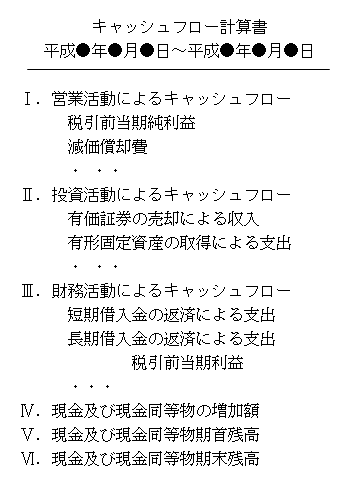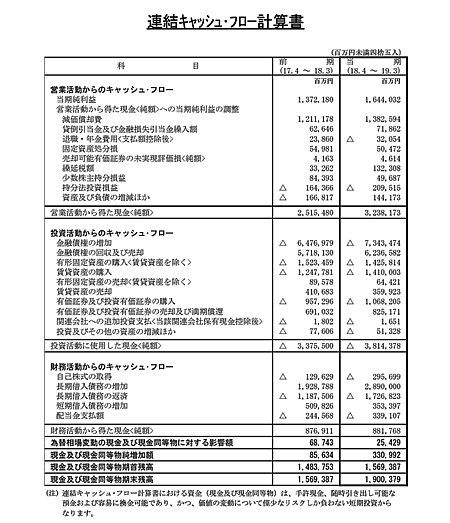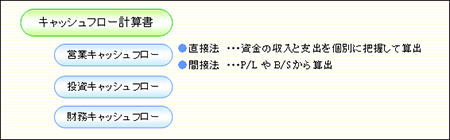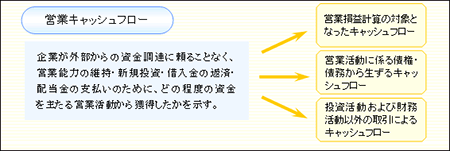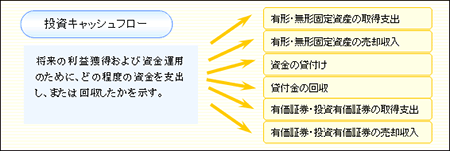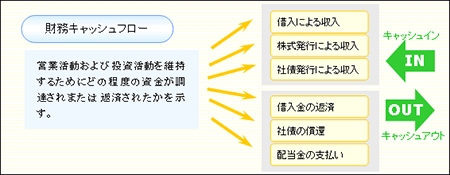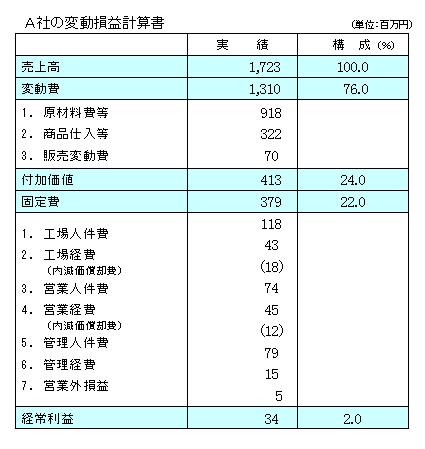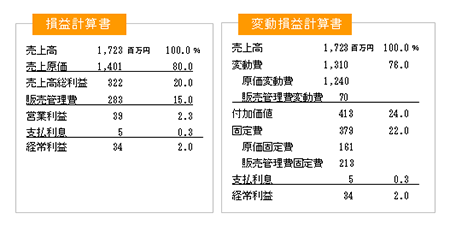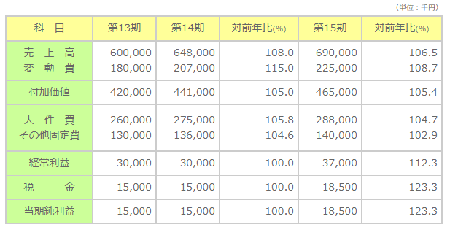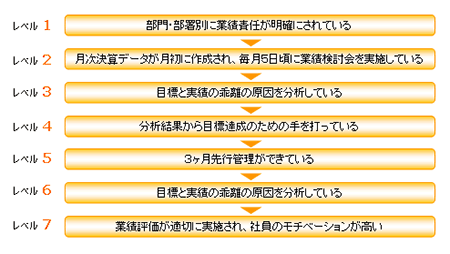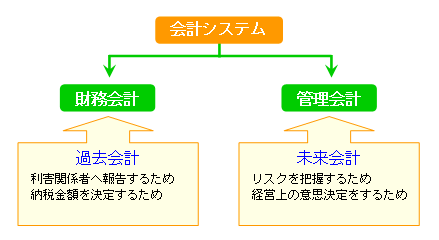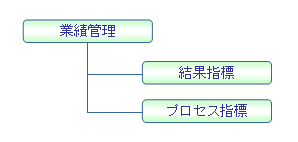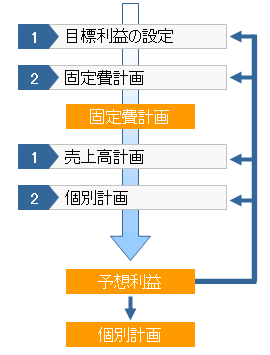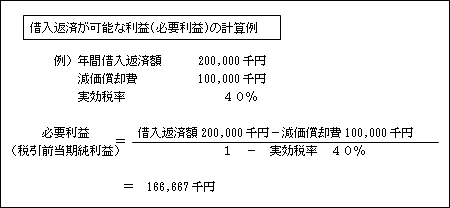1経営幹部が身に付けるべき財務知識とは
決算書の枠組みを理解する
決算書とは一般的に3つの財務諸表を指します。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュフロー計算書
そして、企業に対して決算書作成が義務付けられている理由は2つです。
- 株主に対して自社の財政状況を公開し、株主の保護を図る
- 税務署への税金の申告をする
法的には上記2点の目的を果たすために決算書を作成しますが、この決算書は経営幹部にとっても大きな意味を持ちます。
決算書を正しく理解し、分析することによって、自社の財務上の問題点を抽出することができるからです。そして、財務上の問題点を正しく把握することができれば、今後どのような取り組みをするべきかという「経営課題」を設定することができます。
決算書は会社の問題点の8割方を示してくれます。決算書が発しているメッセージを的確に受け止められる能力があるかないかによって、自社の運命は大きく左右されるのです。
そのために、まず最初は「決算書」の構成を理解するところから始めます。
損益計算書は1年間の実績を示す"自~至"
損益計算書は、期首から期末までの一定期間内の損益の状況を表現するものです。通常は1年間を決算期間として、1年間の事業活動の損益状況を計算します。
損益計算書は、1年間に発生するすべての収益とすべての費用を記載して、経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期利益を表示し、さらに当期未処分利益を記載するという形式を取ります。
損益計算書の特色は、1年間という期間に限定されており、毎年リセットされるという点です。
貸借対照表は会社の歴史すべてを示す"○年○月○日現在"
損益計算書は1年間という期間で区切った計算書であったのに対して、貸借対照表には期間の特定がありません。
貸借対照表は、事業年度の期末日時点での財産の状況を示すものであり、自社設立時から現在まで、延々とつながっているものです。したがって、貸借対照表にはこれまでの自社が取り組んできたすべての活動結果が反映されているということになります。
貸借対照表は、資金の運用結果である「資産の部」と、資金調達の源泉である「負債の部」「純資産の部」に分けられます。
キャッシュフロー計算書は資金調達の健全度を示す
キャッシュフロー計算書は、1年間の「資金の流れを表す決算書」です。
公開会社のみ作成が義務付けられている決算書類ですが、株式非公開会社でも広く作成されているため、経営幹部にはキャッシュフロー計算書に関する知識が求められます。
キャッシュフロー計算書は、本業による資金の流れを示す「営業キャッシュフロー」、投資活動の資金の流れを示す「投資キャッシュフロー」、借入れ、返済などの財務面の資金の流れを示す「財務キャッシュフロー」から構成されます。3つのキャッシュフローの関係を見ることにより、資金調達の健全性を示すことになります。
貸借対照表と幹部の責任の関係を理解する
損益計算書から貸借対照表重視の経営へのシフトが必要
一般的に決算書というと「損益計算書」をイメージするのではないかと思います。損益計算書は1年間だけの活動結果を示したものであり、これまでのすべての事業活動結果を反映したものではありません。
この意味において、貸借対照表は損益計算書よりも自社の長期の活動結果を反映したものとなっています。
また、損益計算書からは自社の収益性の把握はできますが、経営の健全性や安定性を把握することはできません。従って、貸借対照表を読めるようになることは、自社の将来を考える立場にある経営幹部にとって、必須のスキルであるといえます。
貸借対照表を構成する5つの区分とその内容
貸借対照表は左右に分かれ、合計数値は左右で一致します。そのため英語ではバランスシート(B/S)といわれます。
右側は資金の調達である「負債の部」「純資産の部」で構成されます。左側は資金の運用である「資産の部」で構成されます。負債の部は更に「流動負債の部」「固定負債の部」に分かれます。資産の部も「流動資産の部」と「固定資産の部」に分かれます。
したがって、貸借対照表を重要度の高い項目で大きく捉えると、5つの区分で構成されていると見ることができます。
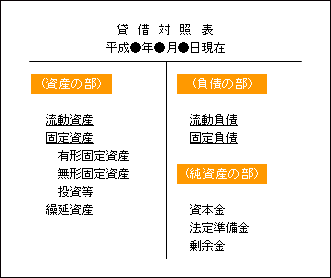
①貸借対照表の配列基準
項目や科目の配列方法については、流動性の高い科目から順に配列する流動性配列法が一般の慣行になっており、企業会計原則においても、原則として流動性配列法によるとされています。
②資産の種類と定義
資産は、流動資産、固定資産および繰延資産の3つに大別されます。流動資産と固定資産については、ワンイヤールールと正常営業循環基準とによって分けられることになります。
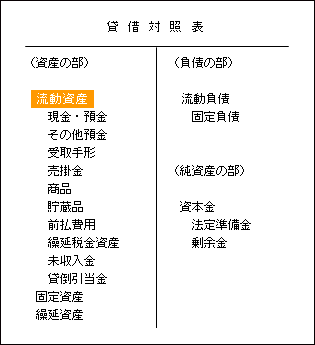
【流動資産】
1年以内に回収されるか、支払われる資産
◇現金・預金
現金及び当座預金、普通預金、通知預金、郵便貯金等
◇その他預金
定額預(貯)金、積立預(貯)金
◇受取手形
得意先との間の通常の取引結果生じた手形上の債権額(取引不能見込み額及び金融手形上の債権を除く)
◇売掛金
得意先との間に通常の取引の結果生じた営業上の未収金(取立不能見込み額は除く)
◇商品
通常の営業過程において販売するために保有するもの
◇貯蔵品
商品の包装材料などでストックしているもの
◇前払費用
前払費用は、前払利息、前払保険料、前払賃借料などのように、一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われている対価をいい、期末の決算整理に際して計上されるもの
◇繰延税金資産
税引前当期純利益に対応するよう調整配分される損益計算書上の税金のうち、翌期以降に期間配分するために貸借対照表上に計上される前払税金をいう
◇貸倒引当金
将来の貸倒見込み額に対する引当金。金銭債権を評価する役割を果たす引当金で、資産の部に評価勘定として計上する。(評価性引当金)
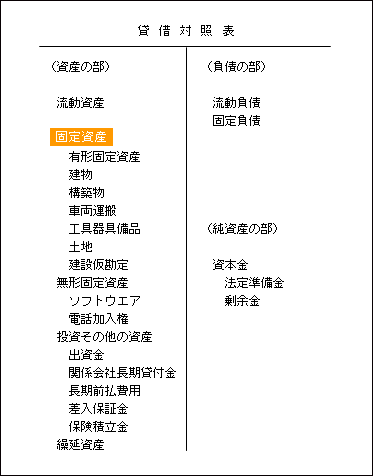
【固定資産】
自社に投下された資本のうち、通常の営業過程において使用または利用することを目的として長期的に所有する資産、長期の利殖のために所有する資産、他社を支配統制するなどの目的で所有する有価証券、長期債権などが固定資産に属する。
◇建物
建物本体のほか、冷暖房設備、照明設備、昇降機などの付属設備も含まれる
◇構築物
煙突、門塀、舗装、軌道、ドック、橋など土地に定着したもので、建物以外の土木設備または工作物をいう
◇機械装置
通常の機械装置のほか、コンベア、ホイスト、起重機などの搬送設備その他の付属設備も含まれる
◇車両運搬具
鉄道車両、自動車などの陸上運搬具をいう
◇工具器具備品
耐用年数1年以上のもので、相当価額以上のもの
◇建設仮勘定
有形固定資産を建設するための支出、および建設目的のために充当した材料を一時的に計上する仮勘定であり、建設が終わりその取得価額が確定した段階で、それぞれ本勘定に振り替えられる
◇無形固定資産
他者に対して長期に特定の商品、製品の製造、販売等に関して他を排除し、または他より優先的地位を確保させることにより、優先的地位を確保させることによって資産としての価値を生じさせるもので、営業権、特許権、借地権、商標権、実用新案権、漁業権、電話加入権などがある
◇投資その他の資産
子会社株式(出資金)または社債、親会社子会社長期貸付金、投資有価証券、差し入保証金、敷金、投資不動産、長期貸付金、長期前払費用などがある
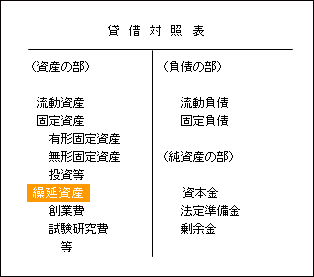
【繰延資産】
すでに代価の支払いが完了し、または支払い義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたっては発現するものと期待される費用は、繰延資産として貸借対照表上に計上する。
◇創業費
創業費とは会社設立のために必要な支出額をいい、印刷費などの設立費用、発起人報酬、定款の認証手数料、設立登記の登録免許税がある。
◇研究費
新製品または新技術の研究のために特別に支出した額をいう。特別に支出した研究費、開発費は、それらの研究開発が成功すると将来の収益の増加や費用の削減などの効果が発現することから、繰延資産とし計上し、5年以内に均等額以上の償却を行う。
③負債の種類と定義
負債は、その調達源泉として計上されるものです。負債は、大別すると、借入金のような債務と、営業上の仕入債務や、役務の提供を必要とする前受けの資金などに分けることができます。
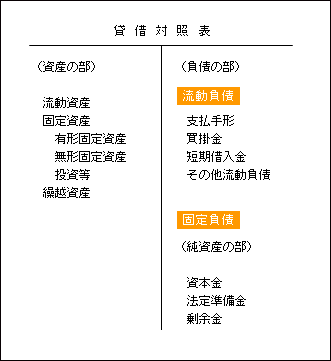
【流動負債】
1年以内に返済しなければならない債務・営業取引上の債務
◇支払手形
仕入先との間に発生した営業取引上の手形債務
◇買掛金
仕入先との間に発生した営業取引上の未払金をいう
◇前受金
将来引き渡すべき商品などの代価の前受額
◇短期借入金
通常の借入金で決算期から起算して1年以内に支払を要する借入額(金融手形上の債務を含む)
◇未払金
固定資産や有価証券の購入など、営業外の取引によって生じた未払債務
◇預り金
他人から金銭などを受け入れ、後日これを原則的にその者に返還することを要するものをいう
◇未払費用
未払賃金、または給料、未払賃借料、未払利息など
◇未払法人税
その事業年度の利益に対して課せられる法人税、法人住民税および事業税の未払い額
【固定負債】
1年以上の将来にわたって返済しなければならない債務・営業取引上の債務
◇長期借入金
株主、役員、従業員又は関係会社からの借入金を除いたもので、決算期末から起算して支払期限が1年を超える債務額(金融手形上の債務を含む)
◇その他固定負債
株主、役員、従業員又は関係会社からの借入金で決算期末から起算して支払期限が 1年を超える債務額、社債など
④純資産の種類と定義
事業を興し、日々の経営活動を行うためには資金が必要です。この資金のうち事業主が出資した資金や株式として出資者から集めた資金、また利益処分後、社内に留保された利益のことを純資産といいます。
純資産は現金や商品のように具体的な財産ではなく、抽象的概念であるため、一般的には資産と負債の差額として把握されています。
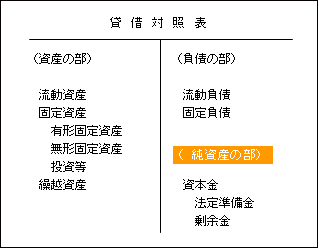
【純資産の部】
返還義務のない自社の資本
◇資本金
株主が実際に出資した資本
◇準備金
会社法によって社内に留保することが義務づけられており、企業の自由裁量で処分することのできない資本。
例)資本準備金、利益準備金
◇剰余金
商法によって拘束されておらず、企業が任意に積み立てあるいは処分できる資本、並びに処分せずに次期に繰り越す利益
例)積立金、繰越利益、未処分利益
貸借対照表の5つの区分と幹部の責任範囲の関係
これまで貸借対照表のしくみについて解説してきました。貸借対照表の大きな5区分には、それぞれ経営幹部の担うべき役割との関係があります。
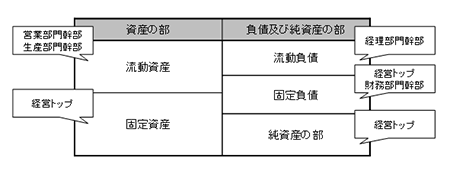
①流動資産
営業活動から発生する売掛金、受取手形、在庫が流動資産の大半を占めます。このことから流動資産の管理責任は営業部門幹部、生産(仕入)部門幹部にあるといえます。
②固定資産
土地、建物といった政策的な設備投資に関する部分が大きなウェイトを占めます。したがって固定資産の管理責任は経営トップにあるといえます。
③流動負債
仕入に対する買掛金、支払手形など、通常の支払いから発生する債務、及び短期借入金が流動負債の中心です。ここは経理部門幹部の責任範囲になります。
④固定負債
設備投資に伴う長期借入金、社債が固定負債です。設備投資判断と一体の問題ですので、経営トップと財務部門幹部の責任となります。
⑤純資産の部
資本金及び利益の内部留保が資本の部です。したがって経営トップの責任となります。
損益計算書とキャッシュフローの関係を理解する
3つの収益、4つの費用、5つの利益
損益計算書は1年間の収益状況を表わす決算書です。その構成は、「収益(収入)」を加算し、「費用」を減算し、その結果発生する「利益」を算出するというものです。
収益には「売上高」「営業外収入」「特別利益」の3種類があります。
◇売上高
一定期間における商品や製品の売上によって得られた営業収益
◇営業外利益
受取利息、受取配当、仕入割引、有価証券売却益、投資不動産賃貸料。有価証券売却益は、原則として流動資産に属する有価証券にかかるものであり、投資有価証券にかかるものは、特別利益として記載される。
◇特別利益
経常外の活動で生じた臨時的な収入で、前期損益修正益、固定資産売却益などが記載される。
費用には「売上原価」「販売費および一般管理費」「営業外費用」「特別損失」の4つがあります。
◇売上原価
当期に販売された商品の仕入並びに製造に関わる費用。
期首商品棚卸高、当期商品仕入高の合計額から期末商品棚卸高を除いたもの。
期首棚卸高
期首において前期末から繰越された棚卸高
当期仕入高
当期に仕入れたもの
期末在庫高
期末における商品の現在額
◇販売費および一般管理費
販売費とは販売に要した費用。一般管理費は企業の全般的な管理に要した費用。
販売費
販売員給料手当、旅費・交通費、通信費、支払運賃、荷造費、消耗品費、広告・宣伝費、交際・接待費、その他販売費。但し、販売業においては支払保管料、車両燃料費、車両修理費を含む。
管理費
役員給料手当、事務員給料手当、賄費、福利厚生費、減価償却費、租税公課、その他営業費。但し、販売業については土地・建物賃借料、保険料、修繕費、光熱・水道料を含む。
◇営業外費用
営業活動外の活動により生じた費用。支払利息・割引料、有価証券の評価損、売買損、創業費償却、社債利息、原材料評価損等。
◇特別損失
経常外の活動から生じた損失、および突発的な損失。
例) 固定資産売却損、火災損失、前期損益修正損
利益には、「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「税引前当期利益」「税引後当期利益」の5種類があります。
◇売上総利益
売上高から売上製品製造原価(商品仕入原価)、消費税を除いた額。
◇営業利益
売上高総利益から販売・管理にかかった費用を控除した利益。
これは、企業が営業活動だけから得た利益を表している。
◇経常利益
営業利益に利息の受取・支払等の営業外の収支を加減した利益。営業活動に加えて、資金の運用活動の結果をも含めた利益を表している。
◇税引前当期利益
経常利益に、通常の経営活動以外に発生した特別の利益(損失)を加減した利益をいう。
◇税引後当期利益
税引前当期利益から法人税等(引当額)を差し引いた残りの利益をいう。
利益とキャッシュフローにギャップが生じるワケを理解する
損益計算書は、「収益(収入)」から「費用(支出)」を差し引き、「利益」を計算するものです。普通に考えると「税引後当期利益」=「現金の増加額」となるはずです。
しかし、実際にはそうなりません。その理由は費用の中に現金の支出を伴わないものがあるからです。その代表的なものが「減価償却費」です。また、決算終了後に支払われる「税金」のように、損益計算書への計上時期と資金の流出時期が異なる費用が決算書に計上されています。
このような理由で、損益計算書上の利益とキャッシュフローにはギャップが発生するのです。
そして、利益とキャッシュフローギャップを調整し、わかりやすく表したものがキャッシュフロー計算書です。
キャッシュフロー計算書はその名の通り、貸借対照表や損益計算書のように発生主義ではなく、現金主義を基準にしたものです。
貸借対照表と損益計算書はココでつながる
次に、貸借対照表と損益計算書の関係を見てみます。貸借対照表は期末の「残高」を示したもので、損益計算書は事業年度中の活動結果の「累計金額」を示したものであることは先に触れたとおりです。 企業の事業活動には「掛け」が発生します。売上がすべて現金回収であれば難しい問題は発生しませんが、「売り」には「売掛」「受取手形」が、「買い」には「買掛」「支払手形」が発生します。期中の売上には計上されているが、期末にまだ決済されていない部分がどれだけあるか、というようなものを貸借対照表で表すのです。 また、損益計算書上に計上された「税引後当期利益」は貸借対照表の純資産の部にある「当期未処分利益」へとつながっていきます。このようにして損益計算書と貸借対照表は独立して計算されるものでなく、相互に関係して作成されています。
決算分析は経営課題の80%を教えてくれる
決算書に表わされる経営データは、企業の客観的経営力を示しています。それは、過去の経営努力の度合い、環境への適応度を如実に表わしています。経営成績を大別すると、増収増益、増収減益、減収増益、減収減益の4つのパターンからなり、その大枠から何を読み取るかということになります。
【経営成績の4パターン】
- 増収増益
- 増収減益
- 減収増益
- 減収減益
もし、増収増益であるならば、企業には魅力的な商品・サービスがある、販売体制が良い、などの要因があるはずです。
逆に減収減益の場合には、これまでの取り組みに何らかの問題を抱えている結果であり、必ずどこかバランスを崩している点があるはずです。財務分析で経営特性をつかむことにより、問題点を明らかにすることができ、何を改善すべきかが見えてきます。
このように、決算書は企業の過去の取組みが総合結果として示されるものであり、企業に内在する問題の80%を教えてくれるのです。
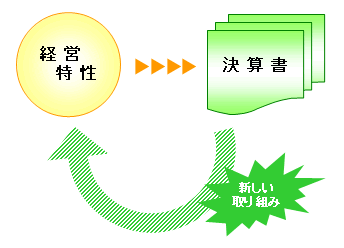
財務分析とは、損益計算書や貸借対照表などの決算書(財務諸表)をさまざまな視点から分析することにより、企業の経営成績や財政状態の良否を判断することに他なりません。
財務分析を大きく分けると、「実数分析」と「比率分析」の2種類があります。実数分析は、財務諸表の実数をそのまま利用して分析します。比率分析は、財務諸表の実数を計算のデータとして使用し、関係比率または構成比率を算出して分析します。
【財務分析】
実数分析
財務諸表の実数を用いて時系列分析する
比率分析
財務諸表の関係比率または構成比率を用いて分析する
【実数分析】
実数分析には、売上・利益増減分析、原価差異分析、経常収支分析、キャッシュフロー分析などがあります。
例えば販売実績を分析するには、販売地域別、営業所別、営業担当者別、商品群別などに区分した期間比較が必要です。このほかに、販売数量の増減による影響と販売単価の変化による影響も分析の対象となります。
増加、減少の要因を分析することによって、どこにどのような問題があるのか、いつまで、どうしなければならないのか、という改善策が明らかになります。
【比率分析】
実数分析は、主に自社の過去データと比較することで増減分析を行うものです。
仮に経営成績の良否の判定を同業他社と比較しようとした場合、業種別の同業他社平均値と比較することになりますが、自社の歴史も違い、又、社員数も異なるため単純に実数を並べても分析にならない場合がほとんどです。
実数を比率に置き換えると、規模の大小にとらわれず比較することができるようになります。これが比率分析の良い点です。
実数分析で自社を絶対評価する
貸借対照表を3期分対比し、資金の調達・運用の実績をみる
【貸借対照表3期分対比】
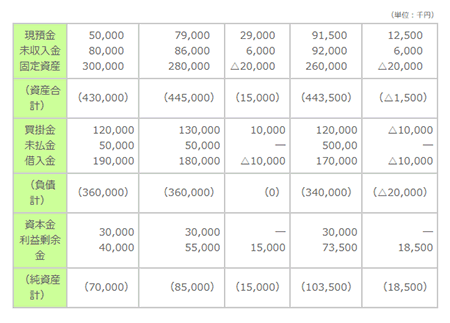
【チェックポイント1】 大枠で傾向をとらえる
①売上高の増加率と総資本の増加率の関係
売上高増加率
>
総資本増加率
…
判定 〇
売上高増加率
=
総資本増加率
…
判定 △
売上高増加率
<
総資本増加率
…
判定 ×
②自己資本比率(総資産に占める自己資本の割合)は高まっているか
【チェックポイント2】 資金の調達と運用(使途)をつかむ
①良好な状態
- 内部留保(利益の蓄積)で設備投資している
- 内部留保(利益の蓄積)で売掛金の増加分を調達している
- 内部留保(利益の蓄積)で在庫の増加分を調達している
- 内部留保(利益の蓄積)で借入金の返済財源を調達している
②好ましくない状態
- 欠損の補填のために支払手形、買掛債務が増加した
- 欠損の補填を資産の処分で行った
- 欠損の補填のために借入金が増加した
【チェックポイント3】 大きな科目を重点的に見る
①資産の部分析
- 総資産の増減はどうか
- 流動資産の増減はどうか
- 売掛債権の増減はどうか
- 仮払金、貸付金、未収金が増加していないか
- 在庫、棚卸資産の増減はどうか
- 固定資産の増減はどうか
②負債の部分析
- 流動負債の増減はどうか
- 買掛債務は増加していないか
- 固定負債の増減はどうか
- 借入金は増加していないか、返済期間は長くないか
③純資産の部分析
- 自己資本は増加しているか
【経営分析フォーマット サンプル】
変動損益計算書を使い、自社の収益性を正確に把握する
(1)変動損益計算書とは
変動損益計算書は、売上高から変動費を控除して付加価値を表示する様式で、直接原価計算様式ともいわれます。通常の損益計算書に比べて利益予測や利益計画に役立つなどの利点があります。
①財務会計における損益計算書の計算式
売上高
-
売上原価
=
売上総利益
売上総利益
-
販売費および一般管理費
=
営業利益
営業利益
+
営業外収益
-
営業外費用
=
経常利益
②管理会計における変動損益計算書の計算式
売上高
-
変動費
=
付加価値
付加価値
-
固定費
=
経常利益
売上高に対する付加価値の割合を付加価値率といいます。
付加価値率
=
付加価値
÷
売上高
×
100
=
(売上高-変動費)
÷
売上高
×
100
=
1
-
変動費率
(2)経営計画策定において変動損益計算書を利用する
A社を例に売上高が10%増加したときの予測をすると以下のようになります。
①財務会計型
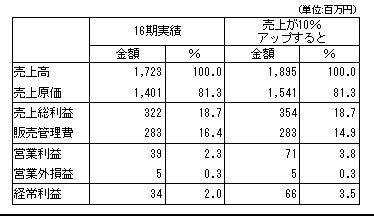
②管理会計型変動損益計算書
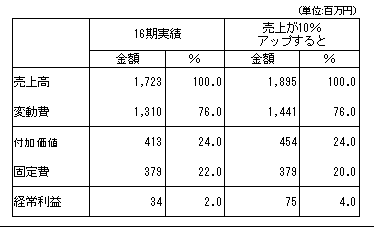
③費用の性質とその分解
売上原価や販売費及び一般管理費の中には、売上高の増減に応じて変化する変動費もあれば、売上高の増減に関係なく毎期発生する固定費もあります。
したがって、費用を変動費と固定費に分けて捉えることによって、自社の収益性をより正確に把握することができます。
また、変動費と固定費では費用の性質が異なるので、経費の削減方法もおのずと異なります。よって、コストダウンを図る場合にも、変動費と固定費に分けて検討することが大切です。
イ変動費
変動費とは、売上高や工場の操業度の変化に伴って比例的に発生する費用で、材料費、外注加工費、荷造包装費、運搬費、残業手当、歩合給などがあります。
ロ固定費
固定費は売上高や操業度の変化にかかわりなく発生する固定的な費用であり、仮に売上がゼロであっても発生する費用です。固定費には人件費、減価償却費、賃借料のほか通常の支払経費などがあります。
ハ準変動費、準固定費
すべての費用項目が、純然たる変動費、固定費に区分できるわけではありません。
電力料、ガス代、水道料のように、基本料金の存在等によって操業度がゼロであっても発生する部分と、操業度の変化に応じて比例的に発生する部分もあるものは準変動費、間接工の賃金などのように、操業度が大きく変化するまでは固定的に発生する費用は準固定費と考え、より実態に合った費用区分をすべきです。
④変動費と固定費の分解方法
変動損益計算書を3期比較し、増減実数・増減割合を分析する
【比較変動損益計算書】

【チェックポイント1】 大枠で傾向を分析する
- 増収増益
- 減収増益
- 変動なし
- 増収減益
- 減収減益
【チェックポイント2】 その傾向の要因分析をする
①損益の傾向
- 売上高の推移はどうか
②三つの利益推移
- 付加価値(=限界利益)の推移はどうか
- 営業利益の推移はどうか
- 経常利益の推移はどうか
③経費の推移
- 変動費の推移はどうか
- 固定費の推移はどうか
- 人件費の推移はどうか
- 人件費以外の固定費の推移はどうか
【経営分析フォーマット サンプル】
キャッシュフローを実数分析する
(1)営業キャッシュフローの構成
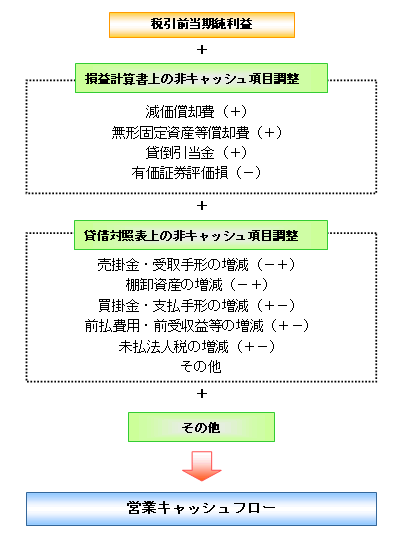
【貸借対照表の項目調整】
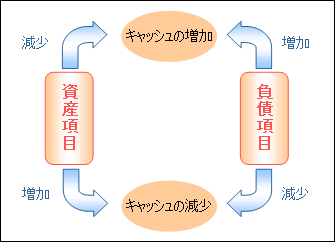
(2)投資キャッシュフロー
①投資CFの増加
- 有価証券の売却
- 貸付金の回収
- 有形固定資産の売却
- 投資等の売却
②投資CFの減少
- 有価証券の取得
- 貸付金の貸付
- 有形固定資産の購入
- 無形固定資産の購入
- 投資等への投資
- 繰延資産の取得
(3)財務キャッシュフロー
①財務CFの増加
- 短期借入金による調達
- 手形割引による調達
- 長期借入金による調達
- 社債による調達
- 増資による調達
②財務CFの減少
- 短期借入金の返済
- 割引手形の返済
- 長期借入金の返済
- 社債の償還
- 減資による支払
- 配当金の支払
【チェックポイント】 その傾向の原因分析をする
①営業キャッシュフローの増減はどうか
②投資キャッシュフローの増減はどうか
③財務キャッシュフローの増減はどうか
④合計のキャッシュフローの増減はどうか
【経営分析フォーマット】
比率分析で自社を相対評価する
比率分析で自社を相対評価する
【収益性分析】
収益力は自社が調達し、経営に投下した資本の運用効率を示す総資本経常利益率によって総合的に評価されます。
またそれは、売上高経常利益率(売上に対する、営業活動によって得た利益の割合)と、総資本回転率(経営に投下された資本を、売上高により回収した速度を示すもの)に分解されます。
収益性をみるために確認する指標
| 分析指標 | 算 式 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 総資本経常利益率 |
経常利益 総資本 |
投下している資本に対して、どれだけの利益をあげたかをみる |
| 売上総利益率 |
売上総利益 売上高 |
すべての利益の源である粗利益獲得力をみる |
| 売上高営業利益率 |
営業利益 売上高 |
粗利益から、販売費及び一般管理費を差引いた「本業の儲け」の割合をみる |
| 売上高経常利益率 |
経常利益 売上高 |
本業に係る自社活動全体から生み出される利益力をみる |
| 総資本回転率 |
売上高 総資本 |
一年間で総資本の何倍の売上高をあげたかをみる |
| インタレスト・ カバレッジ・レシオ |
営業利益+受取利息 支払利息・割引料 |
金融費用の何倍の事業利益を上げているのかをみる |
収益性を高めるポイント
- 収入を増やす(増客および単価の引上げ)
- 変動比率を下げる(付加価値率を向上させる)
- 一人当たり人件費と一人当たり付加価値のバランスをとる
- 適正人員で自社を運営する
- 固定費を削減する
- 在庫の圧縮、遊休資産の処分
- 未収入金、貸付金の早期回収
【経営分析フォーマット サンプル】
安全性を分析する
【安全性分析】
バランスのとれた安定した経営が行なわれているか、自社を取りまく経営環境が変化しても耐えうる力がどの程度あるかを分析します。
自社の財政状態の良否、支払能力の程度をみるものです。
安全性をみるために確認する指標
①短期的な資産の流動性をみる
| 分析指標 | 算 式 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 流動比率 |
流動資産 流動負債 |
短期的負債の支払をカバーできる運転資金状態をみる。 |
| 当座比率 |
当座資産 流動負債 |
短期的な負債に対する直接支払能力をみる。 |
②長期的な資金調達と運用状況の健全性をみる
| 分析指標 | 算 式 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 固定比率 |
固定資産 自己資本 |
自己資本に対する固定資産の割合状況をみる。 |
| 固定長期適合率 |
固定資産 (自己資本+固定負債) |
固定資産に対する調達源泉が適正かをみる。 |
| 自己資本比率 |
自己資本 総資本 |
投下資本に対する自己資本の割合をみる。 |
安全性を高めるポイント
- 不良在庫、過剰在庫の一掃
- 遊休資産の処分
- 固定資産の購入は長期資金で賄う
【経営分析フォーマット サンプル】
生産性を分析する
【生産性分析】
売上高の投入高に対する割合をいい、自社の経営分析体系の中で、収益性分析を補足するものです。
収益性分析においては投入高を「資本」としたのに対して、生産性分析ではこれを「人」又は「物」としている点が生産性分析の特徴です。
生産性向上があれば、人件費や諸経費の増加を吸収することができる。
生産性をみるために確認する指標
| 分析指標 | 算 式 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 付加価値率 |
付加価値 売上高 |
売上高に対する原価効率をみる。 |
| 1人当り売上高 |
売上高 従業員数 |
従業員1人当りの生産性をみる。 |
| 1人当り付加価値 |
限界利益 従業員数 |
従業員1人当りの生産効率をみる。 |
| 1人当り人件費 |
人件費 従業員数 |
従業員1人当りの人件費水準をみる。 |
| 労働分配率 |
人件費 付加価値 |
社員の生産効率に対する人件費のバランスをみる。 |
生産性向上のポイント
- 人員配置が適正かどうか
- 賃金単価が適正かどうか
- 部門別収益計画が適正かどうか
【経営分析フォーマット サンプル】
成長性をみる
【成長性分析】
自社に投下された経営資産である「人」「物」「金」が、毎年継続的に効率よく活用され、成長、発展に向けての活動がとられているかを分析します。
成長性をみるために確認する指標
| 分析指標 | 算 式 | 利用目的 |
|---|---|---|
| 売上高増加率 |
当期売上高―前期売上高 前期売上高 |
前年と比較した増収状況をみる |
| 付加価値増加率 |
当期付加価値―前期付加価値 前期限界利益 |
付加価値の対前年伸び率をみる |
| 経常利益増加率 |
当期経常利益―前期経常利益 前期経常利益 |
経常利益の対前年伸び率をみる |
| 自己資本増加率 |
当期自己資本―前期自己資本 前期自己資本 |
前年と比較した自己資本の伸びをみる |
成長性向上のポイント
- 新規顧客開拓への取り組み
- 新規分野の提案
- 利益率を増加させる
- 機械化、外注化に取り組む
【経営分析フォーマット サンプル】
損益分岐点分析で自社の採算点を把握する
損益分岐点分析の意義
損益分岐点とは、収益の額と費用の額が等しくなる点、すなわち利益も損失も生じていない売上高、いわゆる採算点をいいます。
損益分岐点は、売上金額だけでなく、工場の操業度や販売個数などによって表すこともできます。損益分岐点売上高は以下のように固定費を付加価値率で除して求めます。
損益分岐点売上高
=
固定費
付加価値率
損益分岐点比率で自社の経営安全度がわかる
現状または想定している売上高が、損益分岐点売上高と比較してどの位置にあるのかを示すのが損益分岐点比率であり、100%から損益分岐点比率を差し引いたものが経営安全度です。
これらは、以下の算式で表されます。
損益分岐点比率
=
損益分岐点売上高
÷
実際売上高(%)
経営安全度
=
(売上高 - 損益分岐点売上高)
÷
実際売上高(%)
損益分岐点比率は低いほうが望ましいといえます。損益分岐点比率が低いということは経営安全度が高いということになり、売上の減少に対する耐力が高いことを意味します。
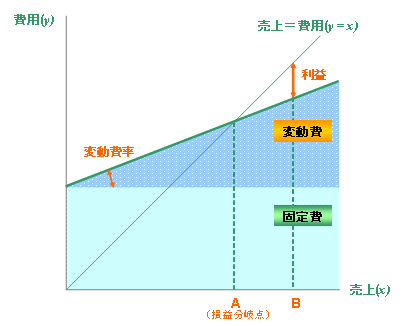
【チェックポイント1】 経営安全率をみる
損益分岐点売上に対して何%の余裕度があるかという、経営安全率を算出し、判定します。
経営安全率(%)
=
1
-(
損益分岐点売上高
実際の売上高
)×
100
損益分岐点分析から判断すべき点
- 収益と費用のバランスがとれているか
- どの商品が利益に貢献しているのか
- 誰が売上に貢献しているのか
- どの地域や店舗が不採算地域なのか
- 将来投資がどの位組み込まれているか
【経営分析フォーマット サンプル】
管理会計で業績を測定し経営改善を図る
最近の経営環境は非常に早く変化します。このような環境下においては、経営幹部だけでなく、社員全員の創意工夫を引き出し、改善意欲、業績向上への執着心を醸成することが必要となります。
そのためには、年度経営計画の進捗チェック、月次計画の進捗チェック、さらには、もっと細かなサイクルを回し、業績向上への善循環を作り出すことがポイントとなってきます。これがまさに業績管理の本質です。
【業績向上への善循環を作り出すポイント】
小さな仮説
⇒
実践
⇒
検証
⇒
軌道修正
しかし、各企業で行なわれている業績管理のレベルはさまざまであり、業績管理がうまく機能している企業は少ないといえます。
例えば、前月の実績を確定するのに時間がかかり、月末近くになってようやく前月の検討会が開かれたりしているというようなことです。業績管理をしていても、高い業績を上げられる企業とそうでない企業の格差はどこにあるのでしょうか。その差は「毎月早期に業績の善し悪しの原因を明確にして、当月以降の活動修正に反映できているか否か」ということにあります。
財務会計で業績管理をしてはいけない理由
(1)貸借対照表を3期分対比し、資金の調達・運用の実績をみる
自社の会計は、主として誰が利用するかによって、大きく2つに分類されます。
- 自社外部の利害関係者のための財務(制度)会計
- 自社内部の経営者、管理者のための管理会計
財務会計の目的は、自社の経営状態の開示であり、会社法や企業会計原則などに則って株主や債権者への報告に利用されます。
これに対し管理会計は、経営の実態を捉え、未来のリスクとチャンスを把握し、経営者・管理者の意思決定が適時・適切に行えるようにすることが目的です。管理会計は自社の内部的なもので、財務会計と異なり、法令の定めに必ずしも従う必要はなく、設計は自由であり、実施するか否か自体も自社の判断に委ねられています。
管理会計は自社の未来「リスクを予知」し、成長発展への「意思決定」を図る上で欠かせないものであり、財務会計と同等、あるいはそれ以上の意味を持っています。
財務会計の手法で将来予測をした場合と管理会計の手法で将来予測をした場合では、予測結果が異なります。財務会計で算出した結果では、正しい「意思決定」をできない可能性があります。
したがって、正しい経営判断を下すためには、管理会計による業績管理を行なうことが必須条件であるということができます。
また、業績管理では、結果数値だけを見るのではなく、結果に至る要因となるプロセス指標を管理することが業績向上へつなげるポイントとなります。
財務会計では、費用を「原価」と「販売費および一般管理費」に分けますが、管理会計では、費用を「変動費」と「固定費」に分けます。
その目的は、売上に連動して変動する費用と、売上に関係なく固定的に発生する費用を別に捉え、管理できるようにするためです。
「管理」するということは、「適正な水準であるかどうかを測定し、適正でなければ適正な水準に是正する判断ができるようにする」ということです。
このように考えると、「変動費」と「固定費」の管理の仕方が変わってきます。
変動費は売上に連動して発生する費用ですから、「売上に対する率」で管理します。これに対して、固定費は固定的に発生する費用ですから、「金額そのもの」を管理します。
●変動費
売上に対する率で管理する
●固定費
金額そのもの(実額)で管理する
また、費用管理のポイントとして、金額の大きなものに着目するということが挙げられます。
「自社の三大費用は何か」を明確にして、大きな経費は重点管理することが大切です。
一方で、固定費の捉え方には注意が必要です。固定費は何でも削減すればいいというものではなく、その費用の性質を理解した上で、削減の検討をしなければなりません。固定費は、人件費、節減可能費、利益貢献経費の3つに分類して管理します。
①人件費
人件費は生産性を基準にコントロールします。付加価値に対する人件費割合である労働分配率を一定に保つようにします。
業務内容を分析し、誰でもできるような業務は標準化し、派遣社員やパート、アルバイトへの切り替え、アウトソーシング化することで人件費を変動費化することを検討します。その結果、正社員は付加価値を高める本来の業務に専念することが可能となります。
②節減可能費
戦略性が薄く、企業努力で節減が可能な経費。
事務用品費や光熱費などがこれにあたります。
③利益貢献経費
将来の利益獲得に向けて今投下する費用。
第一は、事業の存続に必要な費用であり、設備投資や定期補修・改修、車輌の買い換えなどがこれにあたります。これらの設備投資は減価償却費として費用化されます。
第二は差別化のための費用です。例えば顧客の支持を得るために質の高い商品・サービスの開発を行う研究開発費などがこれにあたります。
さらに、他社の追随を防ぐために、組織活性化や自社の顧客の囲い込みなど参入障壁を築くための費用があります。ブランド力、自社製品をアピールするための広告宣伝費や社員のレベルアップのための研修費用などがこれにあたります。
部門別業績測定をするための本社経費配賦方法
業績管理の精度を高め、的確な要因分析を行なうためには、部門別の業績測定が必要になります。部門別業績管理を行なう際に必ず問題になるのが、本社経費の配賦基準をどうしたらよいかということです。
本社経費の配賦には納得性の高い根拠を策定する必要があり、納得性の低い配賦基準を設定してしまうと、部門のモチベーションを下げてしまう結果になりかねません。本社経費の一般的な配賦方法は次の通りです。
①売上高基準・売上総利益基準
売上高の実績により本社費を配賦する方法。売上高総利益率に大きな格差があって、売上高では適当でない場合には、売上総利益または付加価値によって配賦します。
非常に分かりやすい配賦方法である反面、問題点もあります。第1に本社費はほとんど固定費であり、固定費を売上高や総利益といった変動する要素で配賦するのは矛盾している点です。第2に売上高の伸長に伴う本社費負担増に対する反発を受ける可能性が高く、逆に売上高を増加させるモチベーションが弱くなるという点です。
②人員割り
人頭割りともいわれ、所属する従業員数を基準として配賦する方法です。全体の人員を100%として、その部門の人員の割合で配賦します。単純明解で合理性も高く実務上、優れている方法です。
その第1の理由は、本社費の約半分は人件費であり、人件費以外の経費も大部分が人の存在によって発生する属人費であることです。
第2の理由は、人員割りによって本社経費を配賦することにより、本社人員の増加を抑制し、生産性向上に向かわせる効果があるということです。なお、パート・アルバイトの人員は、時間外も含め1日あたり8時間で1人として計算します。中堅、中小企業において部門別業績管理を行う際には、最も適した配賦基準です。
③人件費基準
人員構成に部門間の格差が大きいときには、人件費基準を採用します。社員が多い部門と、パート・アルバイトが多い部門を人員割りで費用配賦したのでは不合理であるからです。
人件費基準はこの欠点を解消し、しかも人員割りのメリットをすべてそなえた、最もすぐれた方法といえます。負担すべき部門全体の人件費を100%として、各部門の人件費の割合で配賦します。
④資産残高基準
各部門の棚卸資産、売上債権などの流動資産、あるいは固定資産残高を加えた資産残高による配賦方法です。全体を100%としての配賦率の計算は売上高基準の場合と同じであり、経理財務部門の費用配賦基準に適しています。また、これらの資産を圧縮させる方向に導くメリットもあります。
⑤使用実績基準
すべての本社経費を、それぞれどの部門がどのようなウェイトで使用しているかを個別に判断し、各部門に配賦する方法です。
作業に膨大な時間を要すること、ウェイト付けの基準設定も難しいという問題点があります。
必要利益、必要売上の考え方で年度数値目標を設定する
管理会計の考え方は、年度経営計画の目標利益の設定に活用することができます。
経営計画の本来の策定ステップは、下記のとおり、決算書の配列の上からではなく、下から作成していくべきものです。
最初に利益目標を設定することから始めるのです。
利益目標の設定方法にはいくつもの手法がありますが、最も重要なのは「必要利益」の考え方です。
企業存続のために必要な費用から、必要な利益を逆算する方法です。企業存続のために必要な費用には、「長期借入金返済額」「昇給分人件費」「設備投資における自己資金投入分」などがあります。
【単年度目標利益の設定方法】
①前年実績伸び率
最も簡単な設定方法で、前年実績に対していくら、何%伸ばすかという目標設定
②1人当り目標利益
1人当りの生産効率(労働生産性)から全体利益を算出する方法
③ライバル会社との比較
競合する同業他社又は業界平均の利益と比較して、自社の利益を決定する方法
④売上高利益率
売上高に対して、どれくらいの利益をあげられるかという比率により決定する方法
⑤借入金返済必要利益
必要利益の最も基本的なもの。借入金の返済に必要とされる利益を計算する方法
必要経常利益
=
(借入金返済額-減価償却費)
÷
(1-実効税率)