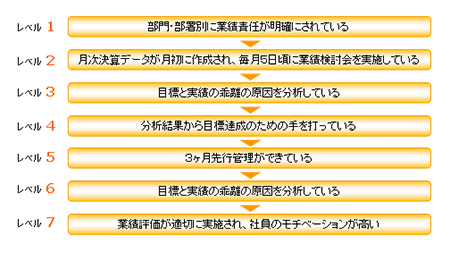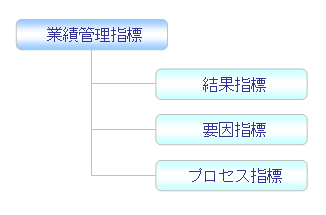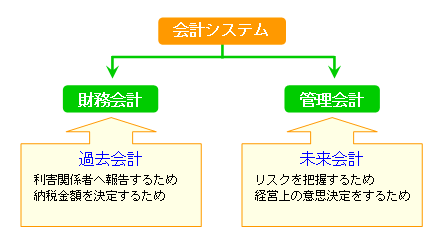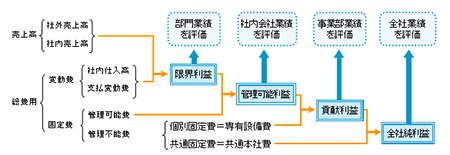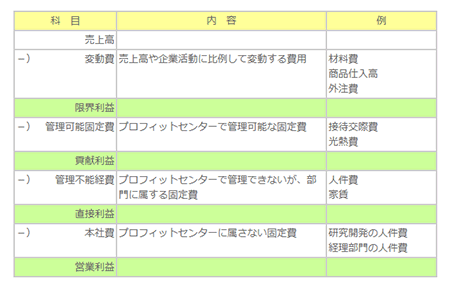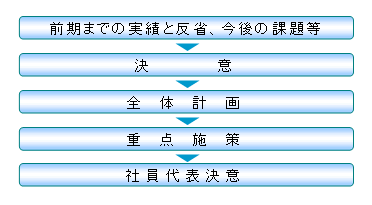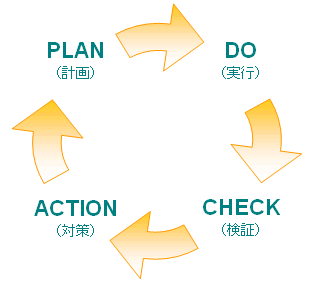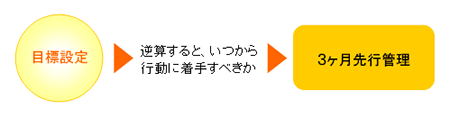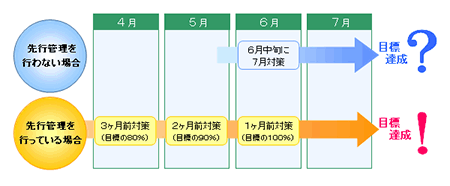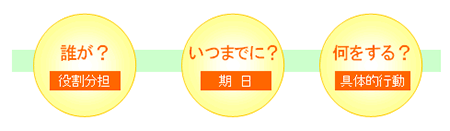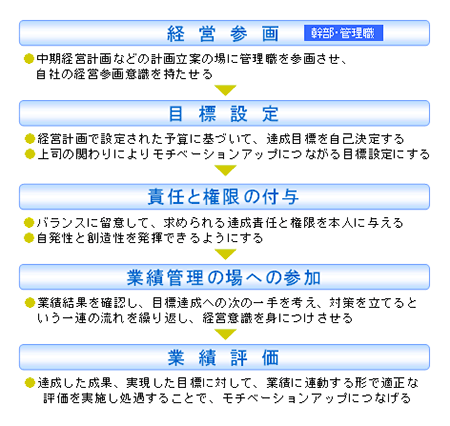2経営幹部が身に付けるべき業績管理
高業績企業における業績管理体制の特徴
業績管理が企業盛衰のカギを握る
高度経済成長期のような右肩上がりの経済成長が望めない経営環境下において、安定的に利益を上げ続けるためには、社員全員の創意工夫や改善意欲、業績向上への執着心を醸成することが必須条件となります。
そのためには、年度経営計画、月次計画を作成した上で進捗チェックのサイクルを回し、業績向上への善循環を作り出すことがポイントとなります。これがまさに業績管理の実践手法です。
【業績向上への善循環を作り出すポイント】
計画
⇒
実践
⇒
検証
⇒
軌道修正
しかし実際には、業績検討会議が単なる予算と実績の差異確認の場になってしまってはいないでしょうか。前月の実績確定に時間がかかり、月末近くになってようやく前月の検討会が開かれたりしている状況ではないでしょうか。
業績管理をすることで高い業績を上げられる企業とそうでない企業の差はどこにあるのでしょうか。その差は「毎月早い時期に業績の善し悪しの原因を明確にして、当月以降の活動修正に反映できているか否か」という点にあります。
業績管理とはなにか
業績管理は、まず数値目標、管理指標、管理項目を設定し、それを実現するための具体的な活動計画を策定することから始めます。
業績管理は自社レベルだけではなく、部門別や課別、チーム別、個人別に細分化し、自社目標と個人レベルの目標へと展開が必要です。その上で目標の連鎖を作り出し、組織全体の目標意識・活性化を図ります。
【業績管理とは】
業績管理とは、企業の経営目標や部門目標達成のための計画を遂行し、その結果である業績を、自社および部門別・管理者別に測定・評価し、次の目標設定・計画策定に活用し、企業目的の達成を図ることである。
業績管理体制の構築
業績管理体制構築の最初のステップは業績責任を客観的に判断できる定量数値(業績管理指標)を設定することです。業績管理指標は3つに大別できます。
【結果指標】
「結果指標」とは、企業活動の結果です。これは「利益」と「キャッシュ」によって捉えられます。
損益項目の結果指標
経常利益の確保(売上高経常利益率)
キャッシュ項目の結果指標
営業キャッシュフローの確保
【要因指標】
「要因指標」とは、結果指標を導く「売上高」や「経費」等になります。
利益は、売上高の確保、変動費の削減(限界利益増加)、固定費の圧縮によって積上げられたものです。要因指標を管理することで結果指標である利益の確保ができます。
また、キャッシュフローの増減に影響する債権回収や在庫回転に関わる指標が「要因指標」です。
損益項目の要因指標
- 売上高の確保
- 変動費の減少
- 限界利益の確保
- 人件費の圧縮
- 人件費外固定費の圧縮
キャッシュ項目の要因指標
- 売上債権(売掛金、受取手形)の減少
- 在庫高の削減
- 買入債務(買掛金、支払手形)の適正化
売上高や利益は下限目標であり、下回ることは許されない「必達目標」です。変動費や固定費などの経費目標は枠内に収める上限目標であり、必守目標ということになります。
【プロセス指標】
プロセス指標とは、要因指標の目標を達成するための活動を明確にしたものです。
売上や利益の目標を設定した段階で目標達成のための必要な活動量は決まるため、この活動の量と質を管理することが必要になるのです。年度活動計画で決定した活動内容を「プロセス指標」として業績管理に含めることが業績向上の重要なポイントになります。
【プロセス指標の具体例】
「結果指標」とは、企業活動の結果です。これは「利益」と「キャッシュ」によって捉えられます。
- 毎月新アイテム3種類の投入
- ○月に○○地域での広告実施
多くの企業では、業績管理が要因指標の把握までにとどまっており、「前月は粗利が未達成だった。来月は必ず達成するように!」という管理になってしまいます。この形での管理では、毎月同じことの繰り返しになってしまい、外部環境の良し悪しに目標達成が大きく影響を受けることになります。
結果指標である経常利益を確実に上げている企業では、結果指標や、要因指標ではなく、プロセス指標の管理を重点的に行っています。常に小さな改善、創意工夫を実施しています。
例えば、新規顧客拡大については、今年度新規顧客による増収をどれだけ見込むのか、その増収部分を商品やサービス単価で割ると何件の新規顧客開拓が必要なのかがわかります。
見込み客のうち、自社の顧客となる確率が10%であれば、20件の新規顧客を獲得するためには200件の見込み客の確保が必要となります。そのためには何件の新規訪問のアポイント数が必要になるか、といったことがプロセス指標となります。
また、既存顧客に対しては、従来通りの取引を維持できたかという点がポイントになります。既存顧客を守るために顧客を取り巻く環境を把握し、ニーズを的確に捉え、ライバル企業の動きを察知し、顧客の課題を解決する商品・サービスの提案をして顧客内シュアを高めることと、顧客を失う原因となるクレームの撲滅を徹底して追及します。
【プロセス指標の例】
●新規顧客開拓活動
- 顧客訪問件数
- 企画提案数
- 有効面談件数
- 新規顧客開拓件数
●既存顧客維持
- 既存顧客継続率
- 既存顧客数
- 自社のシェア率
- 取引数量・単価・粗利益
●新規製品開発
- 新規製品(商品)開発件数
- 新規製品開発レベル
●社員レベルアップ
- スキルマップによる習得度チェック
- 研修回数
- ロールプレイング実施回数
- OJT実施回数
財務会計から管理会計に移行する
管理会計を活用する
(1)財務(制度)会計と管理会計の違い
企業の会計は、主として誰が利用するかによって、大きく2つに分類できます。
●企業外部の利害関係者のための財務(制度)会計
財務会計の目的は、企業の経営状態の開示。会社法や企業会計原則などに則って株主や債権者への報告に利用される。
●企業内部の経営者、管理者のための管理会計
管理会計の目的は、財務会計の実態を捉え、未来のリスクとチャンスを把握し、経営者・管理者の意思決定が適時・適切に行えるようにすること。
管理会計は財務会計と異なり、企業の内部的な目的のために使用するものです。法令の定めに必ずしも従う必要はなく、設計は自由であり、使用するかどうか自体も企業の判断に委ねられています。
しかしながら、管理会計は企業の「未来リスクを予知」し、成長発展への「意思決定」を図る上で欠かせないものであり、財務会計と同等、あるいはそれ以上の意味を持っています。
管理会計の基本は変動損益計算書
(1)変動損益計算書を使い、自社の収益性をより正確に把握する
①変動損益計算書とは
変動損益計算書は、売上高から変動費を控除して限界利益を表示する様式で直接原価計算様式ともいわれる。通常の損益計算書に比べて利益予測や利益計画に役立つなど、戦略的に優れている。
②財務会計における損益計算書の計算式
売上高
-
売上原価
=
売上総利益
売上総利益
-
販売費および一般管理費
=
営業利益
営業利益
-
営業外収益
-
営業外費用
=
経常利益
③管理会計における変動損益計算書の計算式
売上高
-
変動費
=
限界利益
限界利益
-
固定費
=
経常利益
④限界利益とは
限界利益は、売上高が1単位増えるごとの増加利益を表しています。売上高に対する限界利益の割合を限界利益率といいます。
限界利益率
=
限界利益
÷
売上高
×
100
=
(売上高-変動費)
÷
売上高
×
100
=
1
-
変動費率
【例1】
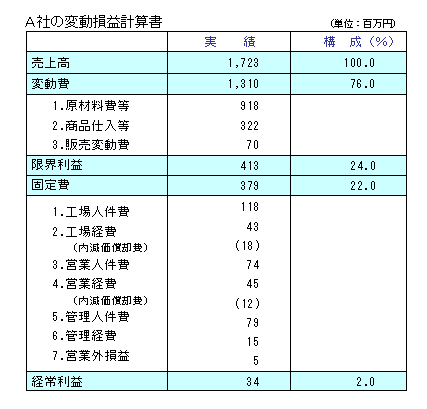
【例2】
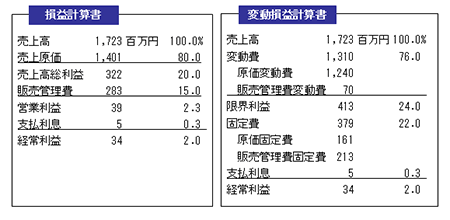
固定費と変動費の考え方
売上原価や販売費及び一般管理費の中には、売上高の増減に応じて変化する変動費と売上高の増減に関係なく毎期発生する固定費もあります。企業の収益性をより正確に把握するためには、費用を変動費と固定費に分けて捉えることが必要です。
また、変動費と固定費では費用の性質が異なるため、削減方法も自ずと異なります。よって、コストダウンを図る場合にも、変動費と固定費に分けて検討することが大切です。
【変動費】
変動費とは、売上高や工場の操業度の変化に伴って比例的に発生する費用で、材料費、外注加工費、荷造包装費、運搬費、残業手当、歩合給などがある。
【固定費】
固定費は売上高や操業度の変化にかかわりなく発生する固定的な費用であり、仮に売上がゼロであっても発生する費用である。固定費には人件費、減価償却費、賃借料のほか通常の支払経費などがある。
【準変動費、準固定費】
すべての費用項目が、純然たる変動費、固定費に区分できるわけではない。
電力料、ガス代、水道料のように、基本料金の存在等によって操業度がゼロであっても発生するものの、操業度の変化に応じて比例的に発生するものを準変動費、間接工の賃金などのように、操業度が大きく変化するまでは固定的に発生する費用を準固定費と考え、より実態に合った費用区分をすべきである。
変動費と固定費の分解方法
(1)個別費用法
費用科目ごとに変動費と固定費を分解するのが個別費用法であり、以下の2通りの方法があります。
- 科目を要素別に分解して固定部分は固定費、変動部分は変動費とする方法
- 科目の性質によって変動費に近いものは変動費とみなし、残りを固定費とみなす方法
固定費と変動費を要素別に分解する方法がより厳密ですが、作成コストや分かりやすさを考慮すれば、変動費を主要なものに絞り、残りを固定費扱いとする簡便な方法で差し支えありません。
(2)業種による分解例
| 小売・卸売業 | 一般製造業 | |
|---|---|---|
| 変動費 | 売上原価+物流コスト+販売手数料 等 | 材料費+外注加工費+工場消耗品費+動力費 等 |
| 固定費 | その他の費用 | その他の費用 |
その他、自社の実状に応じて重要な変動費がある場合は、適宜加えます。
(3)スキャッターグラフ法
過去の実績による売上高と費用合計をグラフにプロットして、売上高の増加割合に応じた費用の増加傾向をつかみ、これから変動費率と固定費を求める方法。
固定費は3つに区分する
固定費は一律に削減すべきものではありません。経営的な視点からメリハリをつけた使い方が必要です。人件費、節減可能費、利益貢献経費の3つに分類し管理します。
【人件費】
人件費は生産性を基準にコントロールする。限界利益に対する人件費割合である労働分配率を一定に保つようにする。
業務内容を分析し、誰でもできるような業務は標準化し派遣社員やパート、アルバイトの活用に切り替えやアウトソーシング化することで人件費を変動費化することができる。その結果、正社員は付加価値を高める本来の業務に専念することが可能となる。
【節減可能費】
戦略性が薄く、企業努力で節減が可能な経費。
事務用品費や光熱費などがこれにあたる。
【利益貢献経費】
将来の利益獲得に向けて今投下する費用。
ひとつには、事業の存続に必要な費用であり、設備投資や定期補修・改修、車輌の買い換えなどがこれにあたる。これらの設備投資は減価償却費として費用化される。
次に差別化のための費用がある。例えば顧客の支持を得るために魅力的な商品・サービスの開発を行う研究開発費などがこれにあたる。
さらに他社の追随を防ぐために、組織活性化や自社の顧客の囲い込みなど参入障壁を築くための費用がある。ブランド力、自社製品をアピールするための広告宣伝費や社員のレベルアップのための研修費用などがこれにあたる。
損益分岐点の考え方を活用する
損益分岐点とは何か
損益分岐点とは、収益の額と費用の額が等しくなる点、すなわち利益も損失も生じていない売上高、いわゆる採算点をいいます。
損益分岐点は、売上金額だけでなく、工場の操業度や販売個数などによって表すこともできます。損益分岐点売上高は、以下のように固定費を限界利益率で除して求めます。
損益分岐点売上高
=
固定費
限界利益率
損益分岐点比率で自社の経営安全度を把握する
昨年度または計画している売上高が、損益分岐点売上高と比較してどの位置にあるのかを示すのが損益分岐点比率であり、100%から損益分岐点比率を差し引いたものが経営安全度です。
これらは、以下の算式で表されます。
損益分岐点比率
=
損益分岐点売上高
÷
実際売上高(%)
経営安全度
=
(売上高 - 損益分岐点売上高)
÷
実際売上高(%)
損益分岐点比率は低いほど、現状または想定している売上高が損益分岐点売上高を上回っていることを意味し、損益構造上望ましいといえます。
経営安全度については、高ければ現状または想定している売上高が損益分岐点売上高に対して余裕を持っていることを表しています。
損益分岐点図で理解する
損益分岐点を求める算式により、損益分岐点を図表化することができます。
この図表により損益分岐点を可視化できるばかりだけでなく、利益を増加させる方法をコスト面からイメージすることができます。
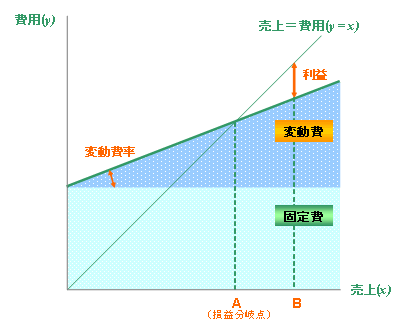
損益分岐点を目標利益設定に活用する
損益分岐点の考え方を活用すると、目標とする利益を実現するために必要な売上高、すなわち「必要売上高」を算出することができます。
損益分岐点売上高の計算式の分子に目標利益を加えることによって、必要売上高を求める計算式に変わります。
必要売上高
=
目標経常利益 + 固定費
限界利益率
部門別、部署別の管理会計システムの導入
管理会計システムを作っていくには、最初に次の事項に留意する必要があります。
- 管理会計システムは財務会計システムからデータを抽出して作成できるように連動させておく
- 原始記録やインプットデータは、財務会計、管理会計を一本化しておく
- 部門別の貸借対照表は必ずしも必要ではないが、売上債権、棚卸資産、固定資産などの主要資産については、分類しておく
- 計算は、正確さよりも迅速さとフィードバックを重視すること
部門別損益計算書ルールのつくり方
管理会計システムで部門別に利益を計算するためには、売上や原価がどこに、どの範囲で帰属するのか、経費はどこの負担になるのかといった、損益計算のルールが必要です。収益と費用の把握および利益の計算の仕方が大きな問題となります。
この計算ルールは、業績管理を進める際にあらかじめ取り決めを行い、業績責任のある経営者、管理者に周知徹底されなければなりません。何よりも計算の仕方によって各部門の利益は大きく相違し、業績評価に影響します。計算根拠が明確になっていないと、不平・不満を招き、モラルを低下させることになります。
部門別損益計算ルールを作る際に特に注意が必要な事項を挙げておきます。
(1)目的の明確化
なぜ、部門別に業績を把握するのか、業績管理の目的は何かをはっきりさせること。個人的な業績評価や成果配分が主目的だと誤解されると社内にアレルギー反応が起こります。本来の目的は以下の3点であることを明らかにしておく必要があります。
- 経営者、管理者が正しい判断、適切な方針を打ち出すため
- 部門運営に対する意思決定を迅速、適切にして、拡大、縮小、撤退などの決定スピードを早めるため
- 部門と部門管理者の業績が正しく把握されることによる責任体制の強化と組織の活性化を図るため
(2)納得の原則
関係者の大多数が「約束ごと」だと割り切って、お互いに納得した上で実施すること。
(3)関係者参画の原則
委員会、プロジェクトチームなどを招集してルールを作るとき、管理スタッフだけでなく、事業部などライン部門からもスタッフを選任すること。直接の関係者が参画すると、納得性が高まりルール遵守意識が醸成されます。
(4)継続性の原則
一度取り決めたルールは期中に簡単に変更しないこと。
むやみに変更を行うと情報資料の継続性を損ね、時系列的な分析、検討ができなくなります。実情に合わなくなった点や実施してわかった不具合を改善するのは当然ですが、それだけに当初のルール作りと会計システムの設計は慎重に行わなければなりません。
(5)適正表示、真実性の原則
意思決定を誤らせないように、利益が正しく計算され、真実の業績が表示されるルールでなければなりません。
「もともと採算のよくない部門だから経費の負担を減らしてやろう」というような姿勢でルールを作ってしまうと、実際の姿を歪めてしまい経営判断を誤らせることになってしまいます。
貢献利益と直接利益
管理可能費と管理外経費
業績管理を進めていく上では、部門でコントロールが可能な経費と不可能な経費の分類が必要になります。
管理可能費とは以下のような特性を持つ直接費です。
- 各部門の構成メンバーが自ら使用したことが分かる費用である
- 当該部門の管理者の責任において、構成メンバー全員により管理可能である
管理外経費は管理不能費ともいわれ、以下のような特性があります。
その部門に発生する直接経費ではあるが、その構成メンバーの努力ではコントロールできない
人件費は本来、管理外経費ですが、パートやアルバイトなどの人件費はコントロールが可能なため、人件費を分けた方がよい場合もあります。
貢献利益と直接利益
付加価値から管理可能費を控除したものが貢献利益です。
貢献利益(管理可能利益)
=
付加価値
-
管理可能費
部門の各メンバーが意識すべき利益が、この貢献利益です。自分たちの努力で変えられる利益が貢献利益だからです。
貢献利益(管理可能利益)から、管理外経費(管理不能経費)を差し引いたものが直接利益です。
直接利益
=
貢献利益(管理可能利益)
-
管理外経費
これは、その部門に発生する直接費のすべてを控除した利益です。
管理・間接費の部門負担のあり方
本社発生費用をどのように扱うか
部門別損益計算を進めるにあたり、本社費の配賦が大きな問題となるケースがあります。本社費の配賦に対する現場の拒絶反応には、次のような理由があります。
- 本社費は事業部などライン部門の権限や努力ではどうにもできないから自分たちの責任範囲外である
- 公平、客観的な配賦基準が見出せない。あるいは社内のコンセンサスが得られない
- 納得のいかない配賦基準による責任外の費用を負担した結果の業績評価は、モチベーションを下げるだけである
このような批判に耐えられるような説得力のある根拠を策定する必要があります。このようなリスクを犯しても本社費を配賦あるいは納付方式によって負担させることのメリットは以下の通りです。
- 業績評価や成果配分のためには直接利益までの計算で十分。しかし収益は発生しないが必要な部門である本社機能はプロフィットセンターである事業部門の収益で賄わないと会社が成り立たない
- トップマネジメントは、本社費負担後の各部門の収益力の評価によって、各部門とそれらを統合した経営戦略の意思決定ができる
- 各部門の管理者に、どれだけの直接利益を上げればよいかの目安を与え、業績基準の裏づけとなる
- 本社費が過大になることに対する批判が生じることで、本社部門効率化への引き金になる。本社部門の予算統制に厳しさを加えるインパクトの効果がある
- 管理、間接部門は、ライン部門に対して中枢管理機能と諸業務集中処理サービスを提供している。サービスの提供に対しては、当然対価を払わなければならない。また対価を支払うことにより、そのサービスを有効に利用する意識が生まれる
配賦方式と納付方式
本社費をライン部門に負担してもらう方法には大別して二つあります。一つは配賦方式であり、もう一つは納付方式です。
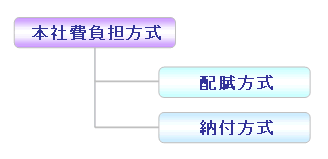
①配賦方式
発生した本社費あるいは発生が予定されている本社費予算額を各ライン部門に設定した基準に基づいて按分して割り掛け負担させる方式。一般的には、この配賦方式が採用されています。
②納付方式
納付方式または納付金方式といわれる本社費の負担方法では、ライン部門が毎月または四半期ごとに所定の基準で計算した金額を本社に納付します。本社部門はこの納付された金額を収益源として発生する費用を負担します。
納付方式では、本社管理、間接部門もあたかもプロフィットセンターであるかのように運営されます。いわゆる擬似プロフィットセンターです。
例えば、事業部制組織で有名な松下電器産業では、各事業部が売上高の3%を本社に納付する方式を長年に渡って採用していました。つまり各事業部の売上高の3%の範囲内で、本社各部門は経費予算を立てることになるのです。
この納付方式では、納付基準となるライン各部門の売上高や資産残高など、一定の範囲内に本社費がおさえられることになります。本社部門が一人歩きして肥大化することを防止できます。
事業部制や分社経営にあたっては配賦方式よりも納付方式を採用して、本社を擬似プロフィットセンター化することが、多くの場合適切です。中小企業においては、本社費がさほど大きくないことから配賦方式が適切です。
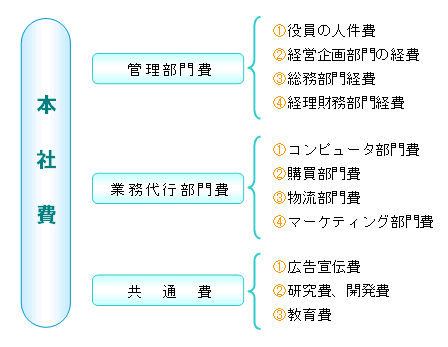
さまざまな配賦基準
本社費をライン部門に配賦する際の基準には以下のようなものがあります。
①売上高基準
売上高の実績により本社費を按分する方法です。売上高総利益率に大きな格差があって、売上高では適当でない場合には、売上総利益あるいは付加価値によって配賦します。 ただし、この方法には難点が目立ちます。第一に、本社費はほとんど固定費であり、固定費を売上高や総利益といった変動する要素で配賦するのは矛盾しているからです。 第二に、売上や利益を伸ばしたら、なぜ本社費を余分に負担しなければならないのかといった反発を受ける可能性が高く、逆に売上高を増加させるモチベーションを阻害する可能性もあるからです。
②資産残高基準
各部門の棚卸資産、売上債権などの流動資産、あるいは固定資産残高を加えた資産残高による按分です。全体を100としての按分率の計算は売上高基準の場合と同じです。経理財務部門の費用配賦基準には適しています。また、これらの資産を圧縮させる方向に導くメリットがあります。
③人員割り
人頭割りともいわれ、所属する従業員数を基準として配賦する方法です。全体の人員を100としてその部門の人員の割合で配賦します。単純明快な上に、理論、実際のいずれからみても優れた方法です。
- 本社費の約半分は人件費であり、人件費以外の経費も、大部分が人の存在によって発生する属人費である
- 配賦されるライン部門の費用も、原材料と商品仕入れを除けば、過半が労務費、人件費である
収益性は、労務、人件費が費用の過半を占めるため、労働生産性が決定的に影響します。人員割りによって、人員の増加を押さえ、生産性を向上させる刺激となります。なお、パート、アルバイトの人員は、1ヶ月の労働時間を基準にして180~200時間程度の範囲内で1人分換算します。
④人件費基準
人事構成に部門間の格差が大きいときには、人件費基準を採用します。ベテラン社員が多い部門と、新入社員やパート、アルバイトが多い部門を人員割りで費用配賦したのでは不合理です。
人件費基準はこの欠点を取り除き、しかも人員割りのメリットをすべてそなえた、最もすぐれた方法です。負担すべき部門全体の人件費を100として、各部門の人件費の割合で按分します。基準とする人件費は基準内賃金と賞与、法定福利費などの固定的部分だけでもよいでしょう。
⑤使用実績基準
コンピュータや物流など業務代行部門費は、相手の部門ごとに使用実績が把握できれば直接賦課(直課)したいところです。使用実績の計算には、たとえば倉庫に保管し出納する商品の個数(量)と金額の割合で概算するといった便宜的な方法を工夫します。
以上述べたように、人員割りまたは人件費基準を原則として、経理部門費については資産残高割りとするなど、必要に応じて他の方法を組み合わせて本社費を配賦します。
研究開発費については、特定部門の特定テーマは経費使用実績で直課するとしても、一般的なものは本社費として人件費割りで配布します。将来の事業分野の開発費に限って、部門直接利益基準で按分することも考えられます。
なお、本社費を配賦する計算実務としては、毎月の実績で変動させる方式と、予算による期中固定方式があります。配賦基準としての人件費などは半期ごとに期首のものをとり、配賦する費用は年度予算とするのが一般的です。
期中固定方式にすると、毎月、あるいは四半期ごとの負担が一定になるため、各部門の業績が本社費負担により変動しなくなり、どれだけの直接利益を上げればよいか明確になるというメリットがあります。
この場合、予算と実績の差額は、年度末に調整するか、本社部門における予算実績の差額としてそのままにしておいても構いません。
納付方式の基準とレート
納付方式を採用する場合、各事業部門が本社に納付する金額は、次の四つの基準のうちいずれか1つ、または2つ以上の組み合わせによります。
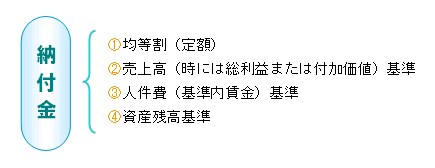
①均等割
たとえば、年間100万円、1,000万円といったように均等割り部分を作ることがあります。これはあくまで納付金額の一部だけとして、大部分は次の②以下の方式によるものとします。
②売上高基準
各事業部門の売上高に対する一定の割合(パーセント)を、本社部門に対する納付金額とします。
各部門の収益構造の相違によって、売上高総利益率、または付加価値率に著しい格差がある場合には、総利益額や付加価値を基準として一定の割合を納付金額としてもかまいません。
この方式によると、本社間接部門は直接部門が実現する売上高の一定の割合の範囲内でその費用を賄わなければならないことになります。松下電器産業を例にとれば、各事業部が売上高の3%を本社に納付し、本社は全売上高の3%以内で運営されることになります。
売上高基準納付方式の問題点は、配賦方式の場合と同様、売上高を伸ばせばそれに比例して費用の負担が増えることにあります。その点、人件費基準や資産残高基準の方が優れているといえます。
③人件費基準
各部門の労務費、人件費に対する一定の割合、たとえば15~20%程度を本社への納付金額とする方法です。
この場合、人件費は支払実績総額をとるよりも、基本人件費としたほうがよいといえます。基本的人件費とは、月例給与、賞与およびこれらに付帯する法定福利費であり、退職金は除外します。賞与は定例賞与(決算賞与は除く)に限定した方が適切です。
この方式によると各部門が生産性を向上させ、対売上または対付加価値の人件費を低下させれば、納付金の負担は相対的に減少します。売上増大、生産性向上への努力が報いられ、これらへの刺激になるメリットがあります。
④資産残高基準
各部門の棚卸資産、売上債権、および固定資産などの残高合計を基準として、その一定割合を納付金額とする手法です。固定資産の少ない業種では固定資産を除外し、棚卸資産と売上債権だけでもよいでしょう。
納付金は人件費基準と資産残高基準で算出する
人件費基準と資産残高基準は、各部門が自らの努力によって本社費の負担を軽減できるため、生産性向上や無駄な資産の圧縮への刺激効果のある優れた方式です。
また、本社管理、間接部門の人員や経費予算額の増加に歯止めをかける効果も無視できません。大企業や完全事業部制、分社経営における本社費の負担方式としては、納付方式が望ましいといえます。
サービス業においては、労働集約性が高いので人件費基準を採用するべきです。在庫や売上債権が多かったり、設備負担が大きい場合には、資産残高基準との併用が適切です。
部門に労働集約型と資本集約型が併存している場合は、資産残高基準と人件費基準を組み合わせれば、納付金の負担は比較的公平になります。
【本社負担金のルール例】
均等割
500万円
人件費基準
各部門の基本人件費として以下の①②の合計額×12%
①給与(残業手当を含む)
②賞与(業績賞与部分は除く)
資産基準
以下の①②③④の合計額 × 10%
①各部門の当期各月末の平均売上債権残高
②各部門当期各月末の平均棚卸資産残高
③各部門当期末の償却資産残高
④各部門当期末のリース資産評価額
業種別業績管理の考え方
部門業績を管理する基本は、変動損益計算書になりますが、業績管理の指標設定は自由であり、業種別に管理すべき項目はさまざまです。業績向上に大きな影響を与える実数や指標、逆に業績悪化に大きな影響を与える実数や指標を重点管理することが大切です。
製造業の場合
製造業は、工場が中心となる業種です。したがって、工場の管理が中心となります。特に経費の中で最も大きい「材料費」や「生産効率」が業績管理の中心になります。
また、見込み生産型の製造業では、製品の改善や新製品の開発が重要なプロセス指標になります。
| 要因指標 | プロセス指標 |
|---|---|
| 売上高 |
・製品別売上 ・新製品投入数 ・製品改善項目数 ・取引先別売上高(受注生産の場合) |
| 限界利益 |
・原材料仕入れ単価 ・工場稼働率 ・パートアルバイト人件費率 ・原材料ロス率 ・外注費率 |
| 在 庫 |
・製品実地棚卸額 ・半製品在庫額 ・在庫回転期間 ・不良在庫額 ・原材料在庫額 |
卸売業の場合
卸売業の経営特性は、「低い限界利益率」、「在庫が膨らむ傾向がある」、「ルート営業中心のため営業担当者に情報が集まる」といった点です。また、取引先が多いという特性もあります。
したがって、上記の項目に焦点を当てた業績管理が必要になります。
| 要因指標 | プロセス指標 |
|---|---|
| 売上高 |
・取引先別売上 ・取引先訪問頻度 ・営業担当者別売上高 ・取引先別案件 ・新規顧客開拓件数 ・営業担当者別案件 |
| 限界利益 |
・商品仕入れ単価 ・商品別粗利益率 ・外注費率 ・取引先別販売単価 ・工場稼働率 ・パートアルバイト人件費率 |
| 在 庫 |
・商品別在庫回転期間 ・不良在庫額 |
| 売上債権 |
・取引先別売掛金残高 ・取引先別売掛金入金状況 |
小売業の場合
小売業は、不特定多数の顧客に対して商品を販売します。したがって、いかに顧客が求める商品を適正な価格で提供するかが大切なポイントになります。また、パートやアルバイトが多いことも業種特性のひとつです。
| 要因指標 | プロセス指標 |
|---|---|
| 売上高 |
・商品別売上高 |
| 限界利益 |
・商品別利益率 |
| 生産性・効率性 |
・人時売上高 ・売り場面積あたり売上高 |
建設業の場合
建設業は、典型的な受注産業です。また、1件当たりの受注金額が大きいこと、収益の確保が現場代理人一人に大きく委ねられていることが特徴です。
| 要因指標 | プロセス指標 |
|---|---|
| 売上高 |
・民間案件情報件数・金額 ・工事現場評価点数(官公庁) |
| 限界利益 |
・実行予算チェック ・現場別月次実行予算差異分析 |
| 効率性・本社固定費経費 |
・社員一人当たり限界利益 ・接待交際費 ・交通費 |
業績を向上させるためのポイント
業績を向上させる仕組みを理解する
(1)利益を確保するために何をすべきか
業績を向上させるためには、利益や売上を確保し、債権回収、在庫回転を管理することが必要不可欠となります。利益を確保するには売上高の確保、経費の削減が考えられます。その中で固定費については戦略的に拡大させる費用、圧縮可能な費用、適正労働分配率でコントロールする総額人件費に分けて考え、一律に削減しないように留意することが必要です。
「ムダ」や「ロス」につながるものは徹底的に削減し、将来への先行投資と捉えられるものは積極的に拡大するといったメリハリをつけた管理がポイントになります。
(2)売上高を確保する
景気の良し悪しにかかわらず、売上を増やすことには困難が伴います。特に新規商品の開発や新規顧客の拡大は難易度が高い項目です。
また、顧客ニーズや嗜好が多様化しているために、マスマーケティングが通用しなくなってきています。ターゲットを絞り込み、ニーズに対する仮説を立て、アプローチをかけるなど効率性を重視した新規開拓手法が求められます。
確実性が高いのは既存顧客との関係を強化し、取引を維持することです。顧客満足度が高まれば新規顧客を紹介してもらえる可能性もあります。そのためにも自社の商品(製品)やサービスを磨き込むことが大切です。
【新規顧客を増やす】
- フェアなどを企画し自社製品をアピールする
- DMを打ち自社製品をアピールする
- 既存顧客の満足度を上げ新規顧客紹介をしてもらう
【既存顧客の購買機会を上げる】
- 既存顧客の満足度を上げリピーター(固定客)化する
- 仕入先・販売先をこまめに回り関係を強化する(リテールサポート)
【販売力を高める】
- 業務の見直しを行い、営業時間の確保をする
- 営業スキルの低い社員に対する教育を実施する
- 成果配分制度の導入によりモチベーションアップを図る
【情報収集力を高め売上拡大のヒントをつかむ】
- 社内情報管理により売れ筋商品を把握し発注・在庫管理をきちんと行い、機会ロスをなくす
- 顧客からの情報収集を密に実施し、マーケットインできるヒントをキャッチする
(3)変動費を削減する
- 外注の社内取り込みにより外注費を削減する
- 原価に含まれる経費(運賃、倉庫保管料等)を削減する
- 不良在庫の早期処分
- ロスを出さないための発注精度向上
- 仕入先との交渉力をつけ、仕入条件を有利に変更する
- 仕入先、販売先のABC分析により利益率の低い取引先の排除と利益率の高い取引先との取引拡大を図る
- 売り切る力をつけ、利益率の高い完全買取条件での仕入を拡大する
- 歩留まりを上げる
- シフト管理によるパート・アルバイト給与の適正コントロールを図る
(4)固定費を圧縮する
- 生産性を分析し人件費を適正化する
- アウトソーシング化、非正社員化による人件費削減する
- 活動計画管理により無駄な残業、出張経費、交通費を削減する
- シフト管理による人時生産性の適正化をはかり生産性向上と人件費コントロール
- ペーパーレス化、社内文書裏紙使用、照明のこまめな節電、事務用品の仕入価格(業者)見直し等で削減可能費を削減する
(5)適正な総額人件費管理を行う
- 適正労働分配率で総額人件費をコントロールする
- 人事・賃金制度を見直し、貢献度反映型へ改正する
キャッシュを確保するために何をすべきか
(1)債権回収を遅らせない
売上が計上されると、損益計算書上では、利益も上がるしくみになっていますが、キャッシュフロー上は売掛金や受取手形が回収されない限り、自社には資金が入って来ません。
営業担当者は売上を上げることに全力を注ぎ、回収まで気が回っていない場合が多く見られます。買掛金の支払いが売掛金の回収より早いと、売上が上がれば上がるほど資金が不足するという現象が起きます。このことを営業担当者に理解してもらい、売上を立て回収して初めて成果であるという認識を持たせる必要があります。
また、取引先に対しては、ビジネスルールを遵守した取引を行い、対等の立場でモノが言える関係を構築し続けることが大切です。こちらの弱みにつけこまれ、入金を先延ばしにされた挙句に、貸倒れで回収不能などといった事態にならないよう、企業コンプライアンスを遵守した誠実な対応を自社員が心がけなければなりません。
【取引先の管理を強化する】
- 取引先の信用調査実施し危険度ランクづけを実施する
- 契約書通りの入金状況か確認する
- 取引が終了した取引先の未回収分の処理を進める
- 回収条件の悪い取引先に対しての条件変更または取引停止を行う
【取引条件の社内的見直し】
- 現金取引比率の拡大
- 手形サイトの短縮
- 回収条件の良い取引先へのシフト
- 社内回収ルールの確立
(2)在庫の回転を早める
在庫が増加するということは在庫に形を変えた固定資金が増加するということであり、倉庫保管料、金利負担などのコストがかかっているという認識をしなければなりません。したがって、販売可能性の高い在庫であれば問題なくても、販売見込みの無い死に筋在庫を抱えてしまった場合には、早急に処分すべきです。資産ではなく費用と捉え、損切りを行なった方が資金繰り上では健全です。
これは、経営トップまたは経営幹部の判断事項です。担当者レベルでは責任を感じてなかなか損切りはできないものです。逆に隠そうとして表面化せずに後で問題化するケースもあります。
見込み型の業種の場合こうした死に筋商品を抱えるリスクは避けられませんが、市場の情報を常時収集し、調整を繰り返すことにより在庫管理の精度を高めておけば、在庫リスクを軽減していくことができます。
【死に筋商品の排除】
- 販売データ管理による月次単位での死に筋商品の処分
- 適正在庫金額の設定とコントロール
【売れ筋商品の絞込みと確保】
- 単品管理を実施し売れ筋商品への絞込み
- 売れ筋商品の量確保と売場展開拡大
【在庫を増やさない】
- 小ロットでのこまめな仕入ができるよう仕入先への条件変更
- 返品可能商品のこまめな返品
- 的確な販売予測ができるよう情報収集し単品管理を徹底する
- 見込み販売から受注販売への転換
業績管理システムを機能させるポイント
経営計画を社内に周知させる
(1)経営計画発表会を実施する理由
経営陣が苦労して策定した経営計画も、社員に理解されなければ意味がありません。そこで、いろいろな策を講じて、社員への周知を図る必要があります。
この手段の一つとして、掲示や配布による周知方法を取っている企業もありますが、「見ていない」「知らない」という社員が必ず出てきます。一番効果的な方法は、経営計画発表会を開催し、経営トップの生の声で、方針と熱意を伝える事です。
(2)経営計画発表会の開催の留意点
- 参加者には事前に経営計画を配布し、目を通させる
- 発表時にプロジェクターなどを使い、全員が理解しやすいよう配慮する
- 発表の流れとしては、まず全体を説明し、次いで部分について話し、最後に全体のポイントをまとめるようにする
あまり堅苦しくならないようにする
式次第にしたがって、司会者を置き、スムーズに進める
- セレモニーとして表彰や記念講演、立食パーティー式の懇親会などをセットする
- 来賓者を招待する場合は、金融機関、関連会社等直接利害関係のある人までとする
(3)社員に経営計画書を配布する
社員全員が計画内容を共有化するために、社員に対し経営計画書を配布します。一方、多くの社員は財務指標等には慣れていないので、文章や数字だけでは理解が進まないのが現実であり、記憶にも残りにくいという実態もあります。
このため、社員に配布する計画書は、イラストや写真、チャート、図表を入れて、できるだけわかりやすいものにするよう工夫する必要があります。
経営計画を経営の共通言語にする
(1)実績や達成状況を定期的に伝える
発表された経営計画の実績や達成状況については、社員の誰もが関心を持ちます。したがって、定期的に伝えることにより、社員のヤル気を高めることができます。
(2)わかりやすく伝える
忙しい時でも時間をかけず理解できるように、グラフや図表によりわかりやすく伝える。
(3)目に付き易いようにする
資料は、会議室、食堂のような場所に掲示したり、社内報やメール等、誰でも目にすることができる媒体を使います。ただし、社外に漏れないよう情報管理には留意しなければならなりません。
(4)進捗状況の把握と共有
年度経営計画には、年度の目標を達成するために実行すべき施策が盛り込まれているはずです。この諸施策の進捗状況を、目標の達成状況と同じように把握することが必要です。
例えば、建設会社で、「原価管理のしくみを作りそれを定着させる」という重点施策を年度経営計画に織り込んでいる場合、実行予算制度の厳格運用、施工検討会の実施、施工工程会議の実施、完工反省会の実施、会社歩掛表の作成、月次決算の実施、下請管理及び仕入管理の強化等の活動計画について実施状況や進捗状況を社員が理解、共有し、推進や改善に参加することが重要なことになります。
先行管理で目標達成に向けてのサイクルをまわす
(1)運用の基本はPDCAサイクル
業績管理運用の基本は、PDCAサイクルです。優れた企業はこのPDCAサイクルが確立されているのです。
具体的には、PDCAサイクルの中で管理会計によってプロフィットセンターを評価するのはC(Check)であり、それに基づいて改善策の構築といったA(Action)に移行します。そのAに基づいて計画の見直しといったP(Plan)に移り、実行D(Do)に移る。このサイクルを毎月実施し、年度目標の達成に向かっていくのです。
業績管理はシステムの構築ステップと運用の段階に分けられます。いくら良いシステムを構築しても、そのシステムが活用されなければ意味がありません。
業績管理項目・管理指標を設定し、部門別の責任体制を明確にした次のステップは、業績管理資料をどのように作成し、どのようなサイクルで点検するかというルールを設定し、管理サイクルを回していくことになります。
PDCAサイクルでいうと、C(検証)とA(対策)に当たる部分です。特に重要なことは、業績検討会議を効果的に実施することです。
(2)業績検討会議の目的
業績検討会議の目的は、過去の実績を要因指標、プロセス指標に分解して把握・分析し、今後の業績向上と管理職の育成に役立てることです。具体的にいうと業績検討会には次に挙げる4つの目的があります。
3ヶ月先行管理を行う作成する資料、発表ともに上記の視点から外れるものは省略し、会議の焦点を絞るべきです。
(3)業績検討会議の基本原則
資料は、会議室、食堂のような場所に掲示したり、社内報やメール等、誰でも目にすることができる媒体を使います。ただし、社外に漏れないよう情報管理には留意しなければならなりません。
【業績検討会 進行例】
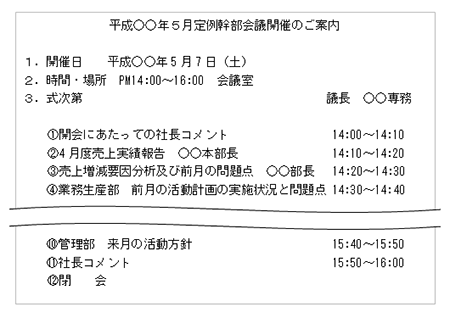
①訓練の場とすること
業績検討会議では、部門の責任者が、実績、要因分析、今後の取組みについて発表し、それに対して質問、議論を行ない、方針が決定されます。
これに基づき、部門内で各人の活動にブレイクダウンされるというステップを踏みます。部門の責任者にとっては、自分の考えをいかに伝えるかという説明能力の訓練の場になります。
経営者にとっては、経営幹部に気づきを与えるコーチングの場になります。部門の責任者の話を聞き、適切な質問を投げかけ、幹部から答えを引き出し、やる気を引き出させ、「考える」経営幹部を育成していくのです。
②実行チェックの場とすること
業績管理はPDCAサイクルの中のCとAが中心となる。まずは、実行チェックをすることが重要です。
業績検討会議の場で、部門責任者が延々と説明・弁解し、経営陣から長時間にわたる質問や追及がなされることが多くあります。業績管理を効率的に、効果的に行うためには、業績管理のフォーマットを統一したり、事前に資料を配布したり、報告のスタイルや持ち時間を決めたりすることが重要なポイントになります。
③意思決定の場とすること
実行チェックの後は、それに基づいて次に何に取り組むのかという意思決定を行わなければなりません。すなわちPDCAサイクルのCからAへのフィードバックです。会議においては、未来に向かった意思決定をすることが最も重要なことです。
効果的な手段としては、会議終了時において意思決定内容を議長が再確認したり、配布される資料に、前回意思決定された項目を記載したりすることです。
④動機付けの場とすること
実行チェックとそれに基づく意思決定がされても、メンバーの納得性が低ければ、期待する結果を出すことができません。すなわちPDCAサイクルのDを促進するような配慮が必要です。参加メンバーが、意思決定された事項の目的をきちんと理解し、達成時のイメージを共有化できるような配慮をすることが大切です。
⑤年度経営計画書を必ず携行すること
業績検討会議では、年度経営計画で設定した目標に対する結果がどうであったかという点についてまず議論が加えられるべきです。したがって、論点の認識の一致をみるためにも年度経営計画書の携行は必須となります。
(4)3ヶ月先行管理を行う
期限までに目標を達成するためには、期限から逆算して、いつから活動に着手すればよいかというスタートラインを決めなくてはならない。一般的には、準備⇒活動⇒成果という1サイクルを回すには、3ヶ月(四半期)単位での先行管理が必要になります。
仮に7月の目標達成のための取り組みを考える時、先行管理を行わない企業では、6月末になってやっと対策を考えますが、もしそこで、この対策が間違っていたら、7月の目標はおろか、その後の目標達成も難しくなってしまいます。
3ケ月先行管理を行うと、3ケ月前の4月に7月の目標達成に向けて第一回目の検討と対策を立て、2ケ月前の5月に第二回目の検討と対策を行うことになりますので、もし立てた対策が間違っていても、軌道修正することが可能となるのです。
目標達成へのステップ
各階層の役割を明確にし、活動計画を策定する
計画を立てる際には社員参加が望ましいといえます。そうしないと目標達成意識が薄れるからです。その際に、経営者はビジョン・方針を明確に示し、それを受けて幹部は戦略を具体化し、管理者・一般社員は具体的活動計画を策定するといった役割分担になります。
特に重要なのが、誰がいつまでに何をやるかという具体的活動計画です。「会社全体の目標・活動計画」⇒「部門の目標・活動計画」⇒「課の目標・活動計画」⇒「個人の目標・活動計画」という、目標・活動計画の連鎖を作り出すことが重要なことなのです。
【活動計画を立てる際の管理者の役割】
- 各担当者別に目標と役割を割り振りする
- 各担当者にそれぞれの活動計画を立てるように指示
- 各担当者から提出された達成計画表をもとに個別のヒアリング
- ヒアリングをもとに活動計画の補足・修正・指導・援助
- 決定した活動計画・目標を集計(計画の承認)
- 経営トップに提出
【活動計画策定のポイント】
社員のレベルアップをはかる
「企業は人なり」と言われるように、人材育成は業績向上のためには避けて通れないテーマです。業績管理の一連の流れの中で、目標を達成するプロセスを体験させることで戦略的な視点を持たせることができます。いかに社員に経営参画意識を持たせられるかということが、人材育成のポイントです。
(1)人材育成のステップ
(2)情報の共有化により「学習する組織」を構築する
通常、組織の中では高い業績を上げられる社員とそうでない社員が混在します。組織全体のレベルを上げていくためには、高い業績を上げられる社員をいかに多くするかということに帰結します。
そのためには、高業績者のノウハウ、成功事例を社員で共有化し、素直に模倣してみることから始めてみると効果が出ます。それにより、成功体験を持つ社員が少しずつ増えてくれば、全体のレベルが底上げされます。また、部門間の壁が高く、隣の部門と顧客が重なり合うにも関わらず、社内では何の顧客情報の交換もできていないということが多々あります。
さらには、他部門の仕事内容をよく把握していないが為に、顧客からの要望に対応できず、機会ロスを生んでいるようなケースもあります。会社全体で、一顧客に対して何ができるかということを考えると、社内でのセクショナリズムは大きな障害であり、マイナス要因にしかなりません。
このような要素を排除するためには、社内での情報共有化の仕組みを構築する必要もあります。
●部門内情報共有化
成功事例・失敗事例の部内での共有化により、社員のナレッジを平準化し自社の強みとする
●他部門情報共有化
セクショナリズムをなくし、会社として顧客に満足してもらうために他部門との顧客情報の共有化をはかる
製造業A社の業績管理事例
【A社の概要】
- 食品系原料の製造業
- 従業員 100名
同業他社は数社しかないが、どの取引先にも全競合が入り込んでいる特殊な業界
業績管理項目の整備
従来は、各部署が独自に考えたフォーマットを作成し、業績検討会議で使用していた。そのため、経営判断に必要な情報が網羅されておらず、会議では、数多くの質問が出され、現状把握だけで多くの時間を費やし、意思決定に至らないことが多かった。
各部にとって重要な指標、項目を整理し、業績管理フォーマットを全面改定。
例えば営業部門では、取引先企業でのシェアを高めていくことが、もっとも重要な項目。日常使用分のシェアは大きく変動することがないため、個別案件(新製品)に対する受注を取ることが重要な業績管理テーマ。このような要素を管理フォーマットに盛り込んだ。
また、前月の総括とあわせ、今後取り組むことを明確にするため、当月取り組むことを記載する欄を作成し、発表することとした。
これにより、結果報告だけの会議から、先行管理型の会議への移行を図った。
会議システムの整備
業績検討会議の議長を社長に変更し、社長の意思が的確にタイムリーに伝えられるように体制を変更。
業績管理フォーマットの整備とあわせ、会議で発表する内容もルール化。各人の発表時間も決め、会議の効率化を推進。前月の総括を発表する時間を3分の1、今月以降の取り組みについての発表を3分の2とするルールにより、部門責任者の視点を過去から未来へ移させることを目指した。
成果
- 業績向上のポイントとなる指標、項目を明確化したことにより、売上高、利益率ともに向上した
- 管理フォーマットの整備により、会議での質問が少なくなり、意思決定にかける時間が多く取れるようになった
- 会議の時間が大幅に短縮された
- 経営者の意思がストレートに伝わるようになった
- 経営幹部の意識が、「過去の分析」から、「これから何をするか」に大きく転換し、戦略思考が浸透した
- 情報の共有化機能が強化され、会社連携の営業体制が取れるようになった
【業績管理フォーマット サンプル】
卸売業B社の業績管理事例
【B社の概要】
- 中堅規模の生鮮食品卸売業
- 従業員:150名
営業部門は取扱商品毎に大きく3つの部門に分かれ、さらに15チームに細分化されている
事業部制による責任会計システムの導入
小売業と産地との直接取引の拡大など、流通構造の変化による卸売市場経由流通量も減少傾向にあり、A社も売上、利益の減少に危機感を感じていた。
組織形態は、取扱商品毎に3つの営業部門に分かれ、さらに15のチームに細分化されていた。中期経営計画は策定しておらず、各チームで売上・利益予算ベースの年度計画は作成されていたが、業績管理のしくみが確立しておらず、売上と営業利益の達成度のみの管理になっていた。
この現状を打破するために、15チームの部門別責任会計システムの導入による部門責任の明確化、中期経営計画の策定による成り行き経営からの脱却、業績と処遇の連動性を高めることによる幹部のモチベーション喚起を図った。
部門別の採算性を重視し、商品ポートフォリオ戦略を明確にするために貢献利益法による責任会計システムを導入した。従来のチーム編成を見直してチャネル別の事業部制組織へ再編成した。
中期経営計画の策定
社員に危機感と目標意識を共有させるために、3ヵ年中期経営計画を策定した。策定にあたり幹部、チームリーダーを策定メンバーに入れて経営参画意識と責任感を持たせた。
年度初めに社員を集め、「中期経営計画発表決起大会」を大々的に実施し、末端社員まで計画内容の理解を深めた。
月次業績検討会実施による進捗管理
毎月10日に月次業績検討会議を開催。チーム別に責任会計指標である売上高、限界利益、管理可能利益を中心に予実対比を確認し、その要因分析と具体的活動計画を検討することにした。
業績評価導入による賃金制度改定
部門別、チーム別、個人別の目標達成度を管理できるシステムを導入。人事考課に反映させ、賞与で賃金に格差のつく体系を構築した。
成果
- 社員へ中期経営計画により自社の方向性を明示したことで、目標達成意識が高まった
- 責任会計システム導入によりチームリーダーの利益概念が変わり、これまで主に変動費管理による営業利益重視だった意識が、管理可能固定費のコントロールにも働くようになり、自部門の自社に対する貢献度合いを考えるようになった
- 各担当者レベルでも売上だけでなく、限界利益を上げることに着目するようになり、取引先への条件交渉強化など活動レベルでの変化が見えてきた
- 活動管理表の毎月作成は最初担当者から「忙しくて書けない」などの抵抗があったが、趣旨の理解が進んでくるにつれて重要性の認識が増した。リーダーが担当者を指導、監督するツールとしても機能している
【個人別活動計画表 サンプル】
小売業C社の業績管理事例
【C社の概要】
- 大手GMSのテナントとして書店を15店舗経営
- 従業員:60名
各店3~6名の正社員とアルバイト、パートで運営。大型店との競合が激化中
日次決算システムの導入
典型的な同族経営であり、業績管理はないに等しい状況であった。社長、社長夫人が各店を回り、個別に指導することが唯一の業績管理。
各店店長を集めた店長会議を開催し、店長間の情報交換による相乗効果を図るとともに、売上げに対する強い意識付けをねらいとした。そのため、日次業績管理システムを導入。また、業績管理フォーマットを整備、ジャンル別の売上を一覧化し、売れ筋商品の顕在化を図った。
書店は、再販制度により販売価格、粗利益がほぼ一定という特殊な業界。そのため、売上とパートアルバイトの変動人件費が分かればほぼ正確に利益が把握できる。
そこで毎日の売上、パートアルバイトのシフト、天候、客入りの動向、店長の感想等を記入するファックス式の日次決算シートを作成。
毎日閉店後、本社へ送信することとした。
翌日までに、経営者が全店のファックスに目を通し、気づいた点、他店へ連絡したほうがよい事項などに対し、タイムリーに対応できるようにした。
店長会議の実施
毎月月初5日までに店長会議を実施することとした。月次の試算表に頼ることなく、ポスレジから出されるデータをもとに業績管理資料を作成。作成する資料は「全店の業績比較表」「店舗別ジャンル別売上構成表」。
また、年度の経営計画を必ず持参し、活動計画の進捗チェックを定例化した。
成果
- 全店の黒字化が実現した
- 日次決算の導入により、経営者の状況判断スピードが大幅にアップした。また、各店への指示がより的確に行えるようになった
- 店長会議で各店の業績が比較されることにより、良い意味で競争意識が醸成された
- 他店の成功体験が共有化されることにより、店長の能力が大きく向上した
- 店舗間の視察が定期的に行われ、売り場改善が進んだ
- 年間の活動計画の実施が完璧に行えるようになった
【ジャンル別売上内訳表 サンプル】
【活動計画進捗チェック用 イベントカレンダー サンプル】
サービス業D社の業績管理事例
【D社の概要】
- 観光ホテルを経営するサービス業
- 客室300室
- 従業員:200名
温泉と景色を売りにする観光地に立地。本州からの旅行客を中心とした顧客構成
5ヵ年経営改善計画の策定
バブル崩壊後、旅行客数の減少により、売上低迷に歯止めがかからず、利益が低水準に陥った。旅行代理店依存の営業体制から、自力で売上、利益を確保する体制へ移行するため、先行管理と部門別売上管理を行うこととした。
また、その前提として、役員全員による5ヵ年経営改善計画を策定し、基本方針を明確にした。
全5ヶ所ある事業所のうち、最も規模の大きい事業所に経営資源の集中配分をすることを決定。2ヵ年は徹底したコスト管理を行い、収益力を向上させる。
3ヵ年は、積極的に戦略的な設備投資を行い、売上増加に取り組む。
業績検討会議の月2回実施
毎月5日、20日の2回、業績検討会を実施し、部門別の業績報告、活動計画の実施状況を確認し、タイムリーに軌道修正できる体制を整備した。
先行管理の導入
ホテル業の場合、商品企画には3ヶ月を要する。旅行代理店依存体質から、自力集客体質へ転換を図るため、3ヶ月先行管理を導入し、毎回の会議で、先行管理中心の議論を行うこととした。
業績管理フォーマットも先行管理を中心としたフォーマットに変更。
幹部教育の実施
業績検討会議終了後、毎回2時間~3時間、部門責任者に対して研修を実施。 テーマは、業務管理、部下管理、顧客満足向上対策と多岐に渡る。
成果
- コストの詳細管理ができるようになり、食材、消耗品を中心としたコストダウンが進んだ
- その結果、売上の大きな伸びがなかった当初2年間でも増益を図ることができた
- 収益体質を強化できたことにより、金融機関との信頼関係が大きく改善し、戦略的な設備投資資金を借り入れすることが可能になった
- 戦略投資がマーケットニーズにマッチし、客単価の向上、集客力のアップにつながり、地域の一番店となった
- 部門責任者の創意工夫が当たり前のものとなり、ホテル内の売店、飲み物などの付帯売上が大きく増加した
- 顧客満足が高まり、リピーター、紹介客が増え、宣伝広告費を抑えることができるようになった
【業績検討会 サンプル】